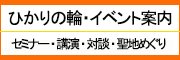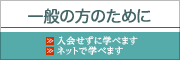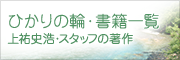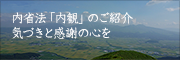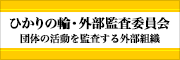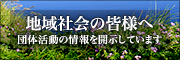アレフをオウム事件の賠償を妨げる「資産隠し」(強制執行妨害罪)の疑いで刑事告発しました
(2025年8月 7日)
1.はじめに
オウム真理教の後継団体・アレフが、2018年以降、オウム事件被害者遺族の方々への賠償金の支払いを停止し、賠償命令が裁判で確定した後も応じない一方で、公安調査庁に教団資産を報告せず、関連事業体を利用するなどして資産を隠し続けて、被害者団体の強制執行も困難な状況となっており、賠償が停滞していることは、今年になって広く報道され(読売新聞の記事1、記事2)、また団体としてもHP記事などで指摘してきました(記事1、記事2)。
さらに、この7月・8月になって、教団を密かに裏から支配する形で、麻原の次男(松本璽暉(ぎょっこう))が教団を主導し、妻(松本明香里(あかり))がその後見人として、賠償の不払い、国への資産の不報告、教団の経理支出等を決定していることが、公安調査庁のアレフに対する再発防止処分請求書によって公表されました(2025年8月4日「官報」)。
そして、ひかりの輪は、このような「資産隠し」は、強制執行妨害罪という刑事犯罪の疑いがあると以前から公表してきましたが、本年3月の読売新聞などの公安調査庁の調査に基づいたアレフの資産隠しに関する前記報道をきっかけとして、脱会した元幹部信者などからの聴き取りを含めて独自の調査を始め、3月までにアレフの本部施設がある埼玉県の警察本部に、麻原次男を含むアレフ幹部を同罪で告発する告発状を提出して、検討いただくとともに、その後もさらに独自の調査を進めてきました(告発が正式に受理されているわけではなく、受理が可能かどうか、その内容を県警に検討していただいている段階です。正式な受理に向けて、ひかりの輪では、さらに必要な証拠収集に努めております)。
ひかりの輪としては、捜査の速やかな進展によって、資産隠しの全貌が解明され、アレフが違法不当な資産隠しを取りやめ、その資産が回収され、被害者の皆さまへの賠償が一刻も早く進むようことを願っています。以下に、本件の告発の概要・理由などをご報告いたします。
2.アレフ教団の資産隠し=資産の強制回収の妨害のために、賠償が完全に停滞していると思われること
公安調査庁のアレフに対する調査や、近年にアレフを脱会した元幹部らによる情報などによれば、以下の事実が認められます。
①オウム真理教事件の被害者団体(オウム真理教犯罪被害者支援機構。以下「支援機構」と記す)は、アレフが2000年に締結した賠償契約の履行に消極的であるため、2012年からアレフとの調停を東京簡裁に申し立て、調停が行なわれてきましたが、2017年末までに決裂しました。
そのため、同支援機構は、2018年2月に、アレフを相手取って、賠償金の支払いを求めて東京地裁に提訴するに至りましたが、同年2018年以降、アレフは一切の賠償金の支払いを停止してしまい、2020年までに賠償支払い命令が最高裁で確定した後も、今現在に至るまで応じることがありませんでした。そして、公安調査庁によれば、この賠償の不払いは、2代目教祖・グルとして教団を主導する麻原の次男により決定され、現在まで維持されたものだとされています(前掲官報)。
そして、公安調査庁の調査やひかりの輪の独自の調査の結果によれば、以下に述べるように、実際には、教団と一体である関連事業体を利用するなどして、教団の資産を隠し、支援機構による資産の強制回収(強制執行)を免れてきた疑いがあります。
さらに、ひかりの輪のアレフ信者の脱会支援活動や公安調査庁の調査の結果によれば、この20年近く、アレフは正体を隠して、オウム事件はオウム以外の者による陰謀だと騙す入会勧誘などで、多くの信者と資金を獲得し、アレフ自らが公安調査庁に報告したところでも、2019年の時点での教団資産は約13億円に上り、その時点での賠償の残債務総額の10億3000万円を優に上回っているという極めて不合理な状況となっていました。
②具体的な強制執行を妨害した疑いに関しては、公安調査庁等の調査によれば、教団は、同年2018年ごろから、一部の教団資産を実質的に教団と一体である関連事業体に移動させるなどして、将来に予想される強制執行(強制的な資産の回収)を妨害する準備とも思われる作業を始めています。
さらに、近年脱会した元幹部信者などの証言によれば、2020年に裁判の判決に基づいた強制執行が開始される状況となると、それを免れるために、あらためて関連事業体の資産を教団の資産ではないと主張して強制執行を妨害するための様々な備えをした疑いがあり、それを現在まで維持していると思われます。
さらに、2021年には、支援機構が賠償の資金を強制回収するために、教団が団体規制法の観察処分に基づいて、その資産等の報告を行う義務のある公安調査庁に対して、教団資産の照会手続きを行なうと、教団は、公安調査庁が同照会に応じて情報提供することは、違法な情報漏洩であるという根拠なき批判を行なった上で、その後、関連事業体などの資産等を公安調査庁に報告しないことで強制執行を妨害した疑いがあります(参考記事)。
そして、この報告不履行に基づいて2023年に公安調査庁が教団に寄付受領と一部施設の使用禁止の再発防止処分を科した後も、教団は現在に至るまで報告不履行を継続しています。そして、公安調査庁によれば、この公安調査庁への不報告も、賠償の不払いとともに、麻原の次男によって決定され、現在まで維持されています。
さらに、2022年にも、教団の債権資産を実質上教団と一体である複数の関連事業体に譲渡すること(債権譲渡)などによって強制執行を妨害した疑いがあります(参考記事)。また、2022年から2024年にかけては、裁判所が教団の資産開示手続のために、教団の代表者の呼び出しを始めると、教団は、かつてなく極めて頻繁に代表者の変更を行ったため、呼び出しができない状態が作られた結果、裁判所が手続きを断念しましたが(参考記事)、この行為も、強制執行の妨害を目的としたものである疑いがあります。
こうして、アレフ教団は、次男を中心として組織的・継続的に、強制執行を妨害をしてきた疑いが認められます。結果として、2019年時点では、教団自身が、賠償残債務総額の約10億3千万円を上回る約13億円の教団資産を公安調査庁に報告していたにもかかわらず、これまでに強制執行によって回収できた金額はわずか約4200万円にとどまり、賠償が大きく停滞するに至っています。
③そして、公安調査庁によれば、2023年3月以降、教団資産等の不報告に対する公安調査庁による再発防止処分によって、教団の寄付受領や施設使用が禁止されたこともあってか、直近2024年においては、公安調査庁が推測する(教団と一体である関連事業体を含めた)教団の総資産が7億円までに減少するに至っています。
しかし、同時に、元幹部からの情報からしても、公安調査庁の調査によっても、再発防止処分下の教団による新たな資金集め(賛助会員制度の導入)は、その実態が不明であるため、現状把握・推測できない資産隠しの可能性も否定できません。こうして、被害者賠償促進のために回収すべき教団資産の確保が急務となっています。
④最後に、次男と同居する自宅において、埼玉県警が今年4月に行った捜索によって、現金数千万円が発見されたことが先月7月の発表・報道で明らかになった麻原の妻に関してですが、2002年以降、アレフ教団から「(妻が描いた)絵画の使用料」の名目で、毎月40万円の多額の資金援助を受けています。
これが、2006年に警察の捜索などで発覚して広く報道された際には、同じく(アレフに籍を置かない)側近信者の資金援助を受けていることが発覚した麻原三女らと共に、被害者賠償を軽視し妨げるものとして被害者関係の方々から批判されました(読売新聞2006年7月20日夕刊、産経新聞2007年3月20日)。そして、この2025年7月、公安調査庁は、麻原の妻と次男は、今現在もアレフからの「多額」の資金提供で生計を立てており、上記の絵画使用料が支払われ続けていること、絵画使用料とは名目に過ぎず、教団からの生活支援金であることは明白と認定して公表しました(前掲2025年8月4日付け官報)。
また、今回の捜索で発見された現金数千万円について、一部報道機関は、自活の気配がないことから、その出所が、以前発覚して批判された絵画使用料ではないかと報じ、被害者賠償を軽視するものとして再び批判されるに至りました(参考記事)。
この状況は、アレフが2018年から賠償をせずに、裁判所の賠償命令を受けても賠償に応じずに、強制執行が開始される時期以降については、単に被害者への賠償を軽視した不誠実・理不尽な行為であるだけでなく、賠償のために教団資産を回収する強制執行を妨げる行為である疑いを禁じえません。
というのは、同庁によれば、麻原の妻は、「アレフの財産の支出について許可を求められてこれを与えたりする」というアレフ教団の経理上の決済を行う権限を持っていたとも認定されており(前掲官報)、アレフ教団から麻原の妻への資金の移動は、事実上、妻自身の意思で継続されていた疑いが濃厚です。
さらに、麻原の妻は、賠償債務を履行せずに強制執行を受ける教団の状況を熟知し、さらには、未払いの賠償支払いの対象の一部であるオウム時代の教団内部殺人事件に自分自身が関与し、その賠償債務の発生の原因に責任がある本人である立場です。
その妻が、強制執行の開始以降も、社会や当局の批判・監視の目を免れるために、教団運営の関与を違法に(団体規制法違反して)隠しながら、絵画使用料を名目とした過剰と思われる生活支援金の支払いを事実上(経費支出を含めてアレフを裏支配する)自らの手で継続し、自らが受け取っていたということです。
そして、2014年以降、次男と交代でアレフ教団の裏関与から離れた三女・長男らとさえ異なって、前記報道のように、自活努力の気配も見られず、当初の40万円から十分な減額があったとの情報もありません。仮に絵画使用料が減額されずに継続されていれば、強制執行の元となる裁判が開始され、教団が支払いを停止した2018年から(公安調査庁が支払い継続を認定した)今年2025年7月までの間には合計3500万円以上と推計され、最初に発覚して社会の批判を浴びた2006年からの19年間では9000万円以上に上ることになります(さらに、絵画使用料以外に教団・信者から資金援助・布施がないということもまた非常に考えにくいです)。
結論として、最終的な判断は司法当局にゆだねるところですが、強制執行の対象となるべき教団の資産を意図して極めて身勝手・不当に、教団の外(=自分の個人資産)に移転して妨害したという疑いがぬぐえません
※注1
公安調査庁が、麻原の妻・次男を教団の構成員として公に認定したのは本年・2025年7月であり、その自宅を教団施設として初めて検査をしたのは同年3月、それを契機に強制捜査で大金が発見されたのは同年4月であるため、それまでの間は、強制執行を行う支援機構から見れば、麻原の妻・次男の自宅は、強制執行の対象とするのは困難であり、教団内から教団外に資金が移動した結果となっています。
※注2:絵画使用料の経緯
2002年12月以来、アレフ教団は、契約に基づいて、麻原の妻に、月40万円を妻の描いた宗教画の絵画使用料を名目とした生活支援金を支払ってきました。額については、契約書に署名した当時の教団代表の上祐は過剰とも感じましたが、麻原家族を高く位置づける教団の信仰が残っていたため、妻の言い値を受け入れました。
その後、2003年ごろから、上祐らの麻原を相対化する教団改革に対して、麻原を絶対とする三女や妻が教団の裏関与を始めて改革を妨げたため、上祐は幽閉状態に置かれましたが、その後、麻原家族支配から脱却して自立した活動を開始し、2006年になって絵画使用料の件が発覚して広く報道されると、賠償が終わっていない被害者の方々からの強い怒りを買う事態となりました。
そこで、上祐らはその打ち切り(ないしは少なくとも大幅減額)を主張したものの、家族に裏支配された教団は「検討する」と言うだけで、それに応じることはなく、上祐は一部メディアでこの問題を告発し(『創』2007年4月号など)、これらの家族の反社会的な行動を一因として、翌2007年にアレフを脱会するに至りました(『オウム事件 17年目の告白』上祐史浩著、扶桑社 2012年刊)。それ以降、絵画使用料の支払いの継続の有無は外部からは確認できませんでしたが、上記の通り、この7月までに、公安調査庁がその継続を確認して公表しました。
なお、絵画使用料はあくまで名目であり、実質は生活支援金です。オウム真理教の教えでは、私有財産の放棄(布施)の教えがあり、個人が作成した絵画や著作物を含め、全ては教団に布施したものと位置づけられ、上祐が知る限り、後にも先にも、一個人に、その絵画や著作物の使用代金を払ったことはありません。
また、使用料の支払い対象とされた妻が描いたとされるシヴァ神の絵画1枚は、教団において一定の重要性はあっても、教団の祭壇に用いられているシヴァ神の絵画ではなく(その絵画を描いた元信者にも絵画使用料など払ったことは当然なく)、教団運営に必要不可欠なものとまでは言えず、40万円の高額で使用の許可を求める、または使用の許可を与えるような合理性はないものと考えます。
そして、麻原の次男・妻は「アレフからの多額の資金提供で生計を立てている」「絵画使用料は名目にすぎず、生活のための資金提供であるということは明白である」と公安調査庁も認定して発表しています(前掲官報記載の公安調査庁の第6回の再発防止処分請求書)。
3.ひかりの輪としての賠償契約とその履行について
こうしてアレフが2018年以降は賠償契約を全く履行しない中で、ひかりの輪は、2009年に同支援機構との賠償契約を締結して以来、同契約の履行を続け、さらには2023年に再発防止処分が科されてアレフによる賠償の再開が絶望視されるようになって以降は、さまざまな関係者の協力を得て、毎月の賠償金支払い額を倍増するなどの努力をしておりますが、アレフとの団体規模が異なるため、これまでの支払額総計は7000万円を超えるに至ったものの、賠償の残債務総額には遠く及ばない状況となっています。
4.強制執行妨害罪の摘発が、賠償の停滞を緩和・解消すると思われること
このような状況のため、強制執行妨害罪で、アレフ教団と麻原家族をはじめとする教団幹部を刑事摘発することで、①教団資産の強制回収を促進し、②麻原家族をはじめとする教団幹部に対して、資産隠しを断念させて、賠償を再開するように強く促すことが、被害者賠償を促進するために必要不可欠だと考えます。
参考までに、麻原の妻は、1995年に教団信者殺害事件で起訴された際は、その賠償金を支払い、出所後に教団に関与せず、麻原と離婚すると、公判中に主張して減刑を求めた経緯がある一方で、出所後は、2003年頃から教団への裏関与を行い、教団は賠償金支払いに消極的となり停止するに至った経緯があります。
この事実を踏まえても、教団の意思決定権を握る麻原家族個人の刑事摘発を厳正に行うことが、教団に賠償支払いを再開させるため有効な手段と思われます(一方、2023年以来の公安調査庁によるアレフ教団への再発防止処分は、今現在に至っても、教団(次男ら)の賠償不払いの姿勢を変えるには至っていません)。
5.麻原家族の教団への影響力を削ぐことで、教団の合法化を促すこと
また、麻原次男らの教団幹部に対する本件告発は、教団を裏支配して、教団の違法行為の主たる原因となっていると思われる麻原家族の教団に対する影響力を心理的・物理的に削ぐことで、賠償不履行・資産隠しに限らず、上記の教団の不法な入会勧誘などの被害や、次男ら教団上層部の違法な教団運営方針に反する言動をなした信者への不合理な処分による信者の心身の健康被害が生じる恐れなどを解消・予防して、教団を合法化する助けとなると思われます。
そして、オウム時代以来、違法行為・犯罪行為をしたいと思って入会した信者などは、一人もいないと私たちは信じています。その中で、麻原・オウム真理教の教義では、2代目教祖・グル・最終解脱者と位置づけられた次男ら、麻原と一体とされた麻原の子女にこそ、重大な犯罪行為を実行・指示する権能があるため、その影響力を削ぐことが、教団の合法化の要であると思われます。
6.ひかりの輪があえて本件を告発する理由
私たちのさまざまな調査(支援機構の理事からお聞きしたこと、アレフ広報HPの記載、近年脱会した元幹部らの証言、アレフと支援機構との間の裁判の資料など)の結果からは、アレフの教団幹部は、支援機構に対して、通常は加害者側が被害者側にとるべき見方・姿勢とは到底思えぬほどに、強い不信感・敵対感情を示しているように思われます。
支援機構の理事には、麻原オウム時代にも教団と闘い、サリン散布殺人未遂事件の被害者となった弁護士の方も含まれており、麻原家族の影響でアレフが麻原とその家族を絶対視する形で運営される中で、麻原オウム時代と同じように、教団の利益に反する弁護士の方々に危険なまでの敵対感情を抱いていることが懸念されます。事実、支援機構のある弁護士の方からは、アレフに対して賠償金支払いを強く求めていく際に、アレフによって身の危険が及ぶことを懸念する声を実際に聴いたこともあります。
また、公安調査庁に関しては、その再発防止処分の取消しを求めたアレフとの裁判においては、教団による資産隠しが強制執行を免れる目的のものであるという主張がなされているものの、ひかりの輪が今年2025年3月時点で今回の告発状を提出した埼玉県警によれば、公安調査庁による告発手続はとられていません。同月に、同庁は、麻原次男宅に初めての立入検査を行おうとしたものの拒否されたため、同県警が家宅捜索を行うと数千万円の大金が発見され、この7月に同庁は、次男と妻を教団の主導者と認定し、教団の寄付の受領、一部の教団施設の使用、新規施設の取得を禁じる6回目の再発防止処分を請求しましたが(参考記事)、一部の報道では、同庁がアレフに対して後手後手に回っているとの指摘もなされている状況です。
以上の経緯からして、アレフによる強制執行妨害の直接の被害者は支援機構ではあるものの、アレフに対する本件の矢面には、過去の贖罪の一環としても、自分たちが立つべきではないかとも考え、ひかりの輪として告発するに至りました。
加えて、告発に必要な情報を集める上において、ひかりの輪は、①アレフと公安調査庁の再発防止処分を巡る裁判などに提出されたアレフの資産隠しに関する公安調査庁の調査・証拠をコピーし精査できる(アレフと共に賠償契約を締結していることなどから利害関係人の立場であるため)、②18年前の2007年までアレフに所属していた関係から、同教団や麻原家族とは長年の対立関係にあるものの、近年脱会した元幹部信者らの一部には接触を得て、告発を助ける情報を得ることができたことや、同じくアレフ教団の教義・組織構造・信者心理も過去の経験から熟知しているという事情があります。
7.国が被害者団体に代わってアレフから資産を回収するべきとの見解と関連して
今年、地下鉄サリン事件から30年の年となり、アレフによる巧妙な資産隠しを踏まえて、被害者の皆様が、国が教団からの資産回収を被害者団体任せばかりにせず、アレフに対する賠償債権を買い取り、代わって教団から債権を回収することを法務大臣に要請されました。本年3月の衆議院法務委員会でも、オウム問題をよく知る有田芳生衆議院議員が同様の主張をされ、最近は産経新聞の社説などでも同様の主張がなされる状況となりました。
そして、こうした国による強制的な債権回収を想定しても、その実現には、教団が強制執行を妨害し、回収すべき資産が回収できなかった事実を立証する必要性があることには、違いありません。直近は教団資産が減少を始めているとの報告があり、新たな資産隠しがされている可能性が否定できない中で、次男・妻の自宅から大金が発見された状況を踏まえると、国による債権買取を待つのではなく、現段階で本件を告発・公表し、各方面からのご協力を賜り、調査・捜査をより迅速に進め、回収すべき資産をいち早く確保することが必要と考えるに至りました。皆様のご理解とご支援を、よろしくお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●本件告発の概要について
以下が、本年(2025年)3月から現在(8月)までにかけて、ひかりの輪が埼玉県警に提出済、または提出中の告発の概要です。
なお、上記本文にも記載のとおり、告発が正式に受理されているわけではなく、受理が可能かどうか、その内容を県警に検討していただいている段階です。正式な受理に向けて、ひかりの輪では、さらに必要な証拠収集に努めております。
第1,被告発人と罪名について
1.被告発人
(1)松本璽暉(ぎょっこう)
(2)松本明香里(あかり)
(3)松本璽暉の意を受けて下記犯罪事実を実行するアレフの幹部出家信者
2.被告発人の詳細
(1)松本璽暉
麻原の次男で、教団で2代目教祖と位置付けられて絶対的な権威を持ち、幹部信者に指示して下記犯罪事実を主導している者。
(2)松本明香里
麻原の妻であり、松本璽暉の実母であり、正大師の階級を持ち、長らく教団を裏から支配し、2014年に松本璽暉の教祖復帰を進め、その後は松本璽暉の後見人として教団を裏支配する者(改名前は知子)。
(3)麻原次男の意を受けて被疑事実の実行をした幹部出家信者
教団の公式の最高意思機関は合同会議と呼ばれるが、上記の通り、それには真実に意思決定権はないので、それに属するか否かを問わず、麻原次男の意を受けて下記被疑事実を実行した幹部出家信者である(主に教団の宗教的な階級では師補以上の階級を有する者だが必ずしもそうとは限らない)。
3.罪名
上記の被告発人らによる次項「第2,5つの犯罪事実など」の1~5に記載した行為は、
①強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)
②組織的な強制執行妨害目的財産損壊等の罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項2号)
に該当する犯罪行為である。
なお、①の刑罰は「3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または併科」であり、公訴時効は「3年」であるが、②が適用されることにより、その刑罰は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」に加重され、公訴時効も「5年」に延びる。
第2,5つの犯罪事実など
1.【犯罪事実1】関連法人の資産を公安調査庁に報告しないことなどにより、様々な手段で強制執行を妨害し続けている疑いがある。
(1)賠償契約の締結
2000年7月6日に、宗教団体アレフ(当時の代表・村岡達子)は、オウム事件の被害者賠償契約を、破産財団オウム真理教(当時の破産管財人は故阿部三郎弁護士)との間で締結した。なお、宗教団体アレフは、教団の執行部の意思決定に基づいて、専ら教団の出家信者を役員・社員とする関連事業体(主に合同会社の形態をとる)をその一部として含むことは、契約締結時の代表者である村岡達子や、その契約を主導し、2004年に同契約を更改した当時の代表者の上祐史浩をはじめ、当時の役員すべての共通の見解である。また、当時の教団は、契約相手のオウム真理教破産管財人の阿部三郎弁護士から、賠償契約の履行のために教団が合法的な事業活動を行うことを認めるという趣旨の一筆を得ているが、これも同関連事業体とその資産が宗教団体アレフの一部であり、その資産の一部である証左である。
また、教団自体も、2000年に団体規制法に基づく観察処分が導入されて以来、2020年ごろから突然報告をしなくなるまでは、その教団資産報告の中に同関連事業体の資産を報告してきた。また、2018年に提起され、2020年に最高裁で確定したアレフに対する賠償命令の判決でも、アレフの関連事業体はアレフと一体であり、その資産はアレフの資産と認定されている。
さらに、2024年に確定したアレフに対する再発防止処分の取消訴訟でも同じく関連事業体はアレフと一体であると認定されている(判決には「本件収益事業は原告(アレフ)が実質的に経営しているものであり、本件収益事業に係る現金及び預貯金等も「団体の資産」として要報告事項となる」と判示されている(令和6年12月17日付け判決の35頁))。
また、宗教団体が賠償契約を締結する際に、それと意思決定機関を共有し、構成員を共有するなど実質的に一体であり、名義のみが異なる事業体をその宗教団体の中に含めない解釈を許せば、宗教団体の性質からして、双方を運営する信者達に指示し、宗教団体の支出ばかり増やし、事業体の収入ばかりを増やすことは容易にできるため、宗教団体の債務の履行を不可能にしたり、強制執行を回避することが自由にできるという不合理が生じるので容認されるべきことではないことは自明である。
(2)次男が主導するアレフの体制とオウム事件の被害者賠償金の支払いに対する否定的な姿勢の形成
アレフには、2003年ごろから、麻原の三女(松本麗華)と妻(上記松本明香理)が、教団に籍をおかずに、裏からその運営に関与してきた(以上は国と三女の間の裁判判決などで明らかであり、これは団体規制法上の構成員・役職員を報告する法的義務に違反した違法行為である)。
ところが、2008年ごろから、麻原家族に裏支配された教団は、被害者遺族団体(オウム真理教犯罪被害者支援機構、以下同支援機構)などよれば、2000年締結した賠償契約の履行が遅れる中で、従来のオウム真理教破産財団を相手とした契約から、その債権債務を引き継いだ同支援機構との契約の締結などに関しては極めて否定的な姿勢をとるようになり、同支援機構はやむなく、2012年から賠償金の支払いに関して、東京簡易裁判所において、アレフとの調停を申し立てた(しかし、これは2018年までに決裂した)。
なお、この間、ひかりの輪は、アレフに被害者賠償を行わせるよう、支援機構に対して、アレフの参考情報を提供する等して協力し続けてきた。
2013年ごろに麻原の次男が教団復帰を意図し、それを妻が支持すると、教団はそれを受け入れ、その後は、三女に交代して、次男と妻が教団の意思決定に裏から関与するようになり、2017年までには遅くとも次男はグルを自称し、自らを2代目教祖と主張し、自分と父親の麻原を一体と見ることを説き、次男と麻原と同じ絶対的な権限を持つ教団の主導者として、その後見人を妻(次男の母)とした体制で、教団は運営されるようになった(以上は2025年7月の公安調査庁の第6回再発防止処分請求書(官報公示)における認定や元幹部によって流出した次男と幹部の会話の音声データなどから明らかである)。
そして、東京簡易裁判所における賠償金支払いの調停に関しても、2018年までに裁判所の調停案をアレフが拒絶して決裂することになり、同年2018年からアレフは一切の賠償金の支払いを停止するに至ったが、この不払いは、上記公安調査庁の再発防止処分請求書によれば、次男の決定と認定されている。
その決定に至る前後には、前記合同会議において、同支援機構の理事の弁護士らが、様々な意味で不誠実であり、教団が賠償金を支払っても、それを被害者に渡さずに、着服する恐れがあるといった荒唐無稽で被害妄想的とも言うべき不信感が、広報・法務担当の幹部信者らによって繰り返し主張され、合同会議のメンバーである幹部信者達がそのような認識に誘導された。
実際に、この頃より、アレフ広報は、加害者側の立場にもかかわらず、支援機構が、アレフらが支払った賠償金を被害者にすぐに配当していないことを公にHPなどで批判した。更に、教団の支払いを2000年以来の賠償契約の趣旨と表現に反して、違法行為に基づく被害に対する支払いを意味する「賠償」ではなく、違法行為に基づかない被害に対する支払いを意味する「補償」であるなどとHPなどでも主張した。これに合わせたかのように、裏合同会議のメンバーと思われる者の中には、賠償金の支払いは「法的責任ではなく道義的な責任にとどまる」とまで主張する強硬派もいた。
なお、この調停の中では、アレフは、後の問題となる関連事業体の資産については、それがアレフの資産ではないとは一切主張していない。それどころか、頭金3億円と毎年4000万の分割の支払いを教団側の和解案として示しており、(この和解案はHPにあり)、この3億円という多額のお金は、その当時の公安調査庁に対するアレフの資産の報告においても、関連事業体の資産を合わせなければ、支払うことができない額と思われる。
(3)2018年から被害者支援機構は賠償支払いを求めて裁判を開始し、アレフは賠償金支払いを一切しなくなった
調停が決裂に終わった後、2018年2月に、被害者支援機構は、賠償金約10億5000万円の支払いを求める訴えを東京地裁に提起した。同年7月には、オウム真理教の開祖・麻原彰晃(松本智津夫)の死刑が執行されたため、松本璽暉が名実ともにアレフの二代目教祖・現教祖、二代目グル・現グルの立場となったと推測される。そして、前に述べた通り、この2018年以降は、アレフは、いかなる名目でも(補償金という名目でも)、被害者の賠償に資する支払いをしなくなった。
この裁判においても、アレフは、同支援機構は信用できない旨の主張を展開したが、2019年の東京地裁判決において当然認められず、2020年末までに約10億3000万円(+利息)の賠償金の支払い命令が最高裁で確定するに至った。しかしながら、その後も、麻原次男は、自らなした不払いの決定を今日2025年まで維持している(上記公安調査庁の再発防止処分請求書より)。当時の幹部(現在脱会)によれば、教団は、先ほど述べた支援機構への強い不信感を維持し、実際に全額を支払おうとすれば教団の施設は全てなくなるなど、丸裸になるとも感じたという。
(4)教団が、2020年以来、関連事業体の資産をアレフの資産ではないと偽り、強制執行を妨害する様々な行為を今も続けていること
第一に、2019年の賠償命令の裁判の地裁判決で、仮執行の権限を得ていた支援機構は、翌2020年1月21日から、教団の資産の強制執行を始めて、同日に教団の北越谷施設で現金3000万円ほどを差し押さえた。
これに対して、元幹部の証言によれば、合同会議では、麻原次男の意を受けたと思われる幹部が「関連法人の資産は(教団の資産ではないので団体規制法上、公安調査庁に)報告する必要がない」などと主張し、法律に詳しくない合同会議のメンバーを欺罔し、合同会議は全会一致で、関連法人の資産を報告しない意思決定をなしたが、その背景には、それ以前に、真の意思決定権を持つ麻原次男による不報告の意思決定があった(上記公安調査庁の再発防止処分請求書より)。
しかしながら、前に述べた通り、①関連事業体の資産は教団の資産ではないといった主張は、前記幹部自身が参加した支援機構との調停、それに続く賠償命令を求める支援機構との裁判でも教団は主張した痕跡は見られず、②その裁判の判決では、当時の関連法人を含めた資産全体が教団の資産と認定され、③2023年に教団が提起した再発防止処分の取り消しを求める訴訟の裁判の判決ではアレフと関連法人は一体であり、関連法人の資産の不報告は教団の資産の報告義務違反と明確に認定されたが、教団は控訴せずに判決が確定している。よって、これは、強制執行を回避するための方便であったことは明らかである。
さらに、麻原家族に近い別の幹部が、合同会議の場でそのメンバーに対して、①今後、強制執行が行われること、②教団の在家信者から寄付収入や物品販売の収入を得る各地の道場施設は、その施設の中のお金は教団のものではないということを前提として、関連事業体のものであると主張し、またその施設の玄関などに関連事業体の事業名を記載した標識を立て、それを外さないことを指示し、③この指示は公にせず信用できる出家信者に限って共有・申し合わせることなどを指示した。
この指示を受けて、合同会議のメンバーは、自分が担当する道場施設・関連事業体において、この指示を実行し、例えば、関東地方のある道場では、合同会議のメンバーである師の階級の出家信者が、その一つ下の位階である師補の階級の出家信者と、その施設のお金はアレフのものではないとする主張することを申し合わせて強制執行に備えた。しかし、実際には、各道場において、そこに通う在家信者や、そこに居住する出家信者が教団に譲渡する金品は、任意の非営利団体であるアレフへの寄付と、営利事業体である関連事業体への支払いの双方があるのが事実であった。
そうした教団の対策の結果、教団信者の居住数が最大規模で、その中には、宝樹社という関連事業体の事務所もある足立の施設では、同社のお金であるとの記載と共に4900万円もの大金が入った紙袋がロッカーの中から見つかるなどした。これを始めとして、名義の問題のために、強制執行による回収がなかなか進まない状況であることが、被害者支援機構の担当者を取材した読売新聞などが報道している。こうして、各教団施設において、関連事業体とその資産をアレフとその資産ではないと偽ることで、教団は強制執行を妨害した。
第2に、支援機構は、強制執行を可能とするために、教団が団体規制法の観察処分で資産報告を義務付けられている公安調査庁に対して、弁護士法に基づく照会手続きによって、教団の資産を照会して、現金、預貯金の口座、不動産資産、債権などの情報を入手し、2021年(令和2年)2月には、出家信者を名義人とする預貯金口座計10口の預貯金全額合計約1100万円を差し押さえた。
これに対して、松本璽暉は、教団幹部と、公安調査庁に団体規制法上の報告義務を履行しない(団体規制法上、教団はその資産、構成員、意思決定などを報告する義務がある)ことを検討し、幹部の中には反対意見を述べる者もいたが、松本璽暉は不法国の意思決定をなした(上記公安調査庁の再発防止処分請求書より)。
また、元幹部の証言によれば、その後に行われたと思われる合同会議においても、麻原次男の意を受けたと思われる幹部が中心となって、公安調査庁が、違法に教団資産の情報を漏洩しているという虚偽の主張をしたり(弁護士法に基づく合法的な照会手続きの存在を隠しながら)、また、②ある麻原家族に近いと思われる幹部が、自分の個人名義の口座が差し押さえられた件に関して(同支援機構が公安調査庁に照会して知った口座である以上、教団と同幹部自身が、団体の資金を管理する口座として公安調査庁に報告していたものであるはずなのに)純粋に個人のお金の口座が差し押さえられたという趣旨の主張をして、合同会議のメンバーに公安調査庁に対する激しい怒りを生じさせたという。
この結果、2021年5月から、強制執行を回避するために、公安調査庁に対する一切の報告を取りやめ(5月と8月の報告を全て不提出)、被害者支援機構が、教団の資産の情報を公安調査庁から入手することを不可能にして、その強制執行を妨害するに至った。
なお、元幹部によれば、これに対して、公安調査庁は、2021年10月に、教団の寄付受領・施設使用・入会勧誘の禁止をする再発防止処分を公安審査委員会に申請する。すると、再発防止処分などないと高をくくっていた教団は驚き、公安調査庁に依然として不十分と指摘されはしたが、慌てて一定の範囲の報告を再開するに至ったために、公安調査庁は、同年11月に同請求をいったん取り下げた。
第3に、その後の2022年に入ると、一定の報告をすれば再発防止処分を受けることはないと高をくくった教団は、アレフの資産を急激に減少させるとともに、関連事業体の資産を急増させ、公安調査庁に報告する資産を急減させ、ほとんどの資産を報告しなくなったが、これも前期の通り、最終的には麻原次男の意思決定だと思われる。
これに対して、公安調査庁は、再発防止処分を科すことを繰り返し警告したうえで、2023年1月に、アレフの寄付の受領と教団施設の使用を禁止する再発防止処分を公安審査委員会に請求し、公安審査委員会はそれを認めて、2023年3月に同処分が決定した。
ところが、この2回目の再発防止処分の際は、元幹部によれば、1度目と異なり、合同会議においても、一部のメンバーを除いては、関連法人の資産の不報告を再考したり、その再開を求めることはなく、強制執行の回避を再発防止処分の回避よりも優先する意思を形成した。これは、麻原次男が、前記公安調査庁の再発防止処分請求書の通り、不報告の決定を維持した目だと思われる。そのため、今現在まで教団の関連法人の資産の不報告は続いており、教団は強制執行を妨害し続けている(また、それに応じて再発防止処分も繰り返されている)。
なお、アレフへの再発防止処分の適用によって被害者賠償の遅れが強く懸念される状況になったことを受け、ひかりの輪は、被害者賠償の停滞を少しでも和らげるために、2009年(平成21年)に支援機構と締結した賠償契約の履行に関して、2023年(令和5年)3月以降は、契約上の義務である年間の賠償額を上回る額を支払うようになった(同年2月までは毎月25万円ずつの支払いだったところを、同年3月以降は毎月50万円ずつに倍増させた)。そして、今現在、アレフが支払いの意思が全くない現状の中で、事件の被害者賠償は実質上、専らひかりの輪のみが背負う状態となっている。
2.【犯罪事実2】関連法人はアレフではないと偽りながら、関連法人への貸し付けや債権譲渡によって、強制執行を妨害した疑いがある
(1)アレフから宝樹社への現金貸付け
公安調査庁の調査によれば、アレフの役員らは、2018年(平成30年)11月1日、アレフの資産である現金2億2200万円をアレフの関連法人である合同会社宝樹社に貸し付けたが、公安調査庁によれば、合同会社宝樹社には、これほど多額の現金は不必要であり、全く不自然なものである。
具体的には、公安調査庁は、①貸付金を用いて施設確保するなど多額の現金を必要とする事実が確認されていない(宝樹社はこれ以前にもアレフから貸し付けを受けたことがあるが、その際は施設確保に多額の現金を使用している)、②金銭消費貸借契約書からも貸し付けの目的が判然とせず月々の返済額すら明らかでない、③同年(2018年)2月に支援機構から賠償支払いを求めて提訴されており、同年7月から翌2020年7月までの間に数億円に及ぶ現金の保管場所の変更など、資産隠蔽とみられる動向があった」などとして、賠償逃れのための資産の保護を目的にしたとも思われると指摘している。
また、合同会社宝樹社について、オウム真理教犯罪被害者支援機構(以下、支援機構という)は、「地下鉄サリン事件などオウム真理教による凶悪犯罪の被害者・遺族からの損害賠償請求や強制執行による差し押さえなどを免れるために設立された法人である」「人的にも財政的にも実質的に支配しているのはAleph(アレフ)である」「Alephはその財産を隠匿し、地下鉄サリン事件の被害者・遺族ら債権者を詐害して、強制執行を回避するために宝樹社を設立した」と裁判で述べている。
(2)アレフの宝樹社に対する債権を他の3関連法人へ譲渡
そして、教団は、2020年以降、前に述べた通り、関連法人の資産は教団の資産ではないと位置づけると、2022年の2月から3月にかけて、上記の宝樹社へのアレフの貸付債権を、教団の関連法人に譲渡した。これを指示した者は、麻原家族に近いある幹部である。
しかしながら、アレフは関連法人の資産報告を2020年以来全くしていないため、この債権譲渡は、公安調査庁や、公安調査庁に照会をする被害者支援機構に対して秘密裏に行われたものである。すなわち、支援機構には、2億2千万円の債権は、その債権者の名義を含めて全く不明なものとなり、そのため強制執行は不可能となった(債権譲渡以前は、教団はアレフの宝樹社への債権として公安調査庁に報告していた)。こうして、教団は再び強制執行を妨害した。
その後、2022年6月の公安調査庁の立入検査によって、この債権譲渡の事実と詳細が発覚した。具体的には、アレフの役員らは、合同会社宝樹社に対する元本を2億2200万円とした貸付金について、
ア 2022年(令和4年)2月7日、このうちの5000万円及びこれに対する利息債権をアレフの関連法人「サポート・オブ・ライフ」に5000万円で、
イ 同年3月19日、1億2000万円及びこれに対する利息債権をアレフの関連法人「キャラバン・エンタープライズ」に1億2000万円で、
ウ 同月28日、残額の2700万円及びこれに対する利息債権をアレフの関連法人「徳行」に2700万円で、
それぞれ譲渡して、教団の資産を隠匿したものと公安調査庁は認定している。
なお、上記のアレフから宝樹社への貸し付け及び、アレフから3つの関連法人への債権譲渡の事実については、公安調査庁がアレフ施設に立入検査した際に、以下の書面を写真撮影し、証拠化している。
・アレフから宝樹社への貸し付け
2018年11月1日付け「金銭消費貸借契約書」
・アレフから「サポート・オブ・ライフ」への債権譲渡(上記ア)
2022年2月7日付け「債権譲渡契約書」
・アレフから「キャラバン・エンタープライズ」への債権譲渡(上記イ)
2022年3月19日付け「債権譲渡契約書」
・アレフから「徳行」への債権譲渡(上記ウ)
2022年3月28日付け「債権譲渡契約書」
なお、これらの債権譲渡について調査した公安調査庁も、一般常識に照らすと不自然な取引であり、教団は、支援機構の申立てに基づき、2020年(令和2年)1月には現金約3000万円が差し押さえられた後、2021年(令和3年)2月には出家信者を名義人とする預貯金口座計10口の預貯金全額合計約1100万円が差し押さえられたことからすると、次なる差押えの対象が、上記債権(貸付金)に及ぶと考えるのが自然であり、上記関連法人等に債権を譲渡することによって、貸付金債権の差押えを回避したものであり、前記債権譲渡に関する一連の取引は、強制執行逃れを目的とした資産の隠匿と言うほかないと断言している。
3.【犯罪事実3】代表者の頻繁な変更によって、強制執行を助ける裁判所での資産開示義務のための出頭を回避し、強制執行を妨害した疑いがある
被害者支援機構が教団の資産を把握して強制執行を行うことを助けるために、裁判所は、アレフの公式の代表者(麻原次男ではなく、アレフの規約上の公式の代表者(表の代表者)である「共同幹事」)を呼び出して、その資産を開示する義務を履行させようとした。
これに対して、元幹部によれば、合同会議のメンバーは、資産開示義務のある法廷に出頭すれば、公安調査庁にも報告しなかった資産を報告しなければならないが、麻原家族に近いと思われる幹部から、出頭の拒否、虚偽の主張、証言の拒否は、刑事罰に問われることを知らされたという。
その後、合同会議は、代表者を極めて頻繁に変更した。具体的には、2022年(令和4年)9月から2024年10月までの約2年間で少なくとも9回、代表者を変更した(職務代行者の就任も含めれば13回。この間、代表者を務めたのは5人で(職務代表者を含めれば6人)、特に2024年2月から10月までは、ほぼ毎月変更した)。
その結果、裁判所が、同支援機構が官報などの公開された情報から知りえた当時の教団の代表者の情報に基づいて代表者の召喚状を送付しても、その時の実際の代表者を呼び出すことができない形となり、3回の召喚は機能せず、やむなく裁判所は資産開示手続を終了せざるをえなくなった。
この点に関して、同機構の中村裕二弁護士は「強制執行を逃れるために代表者をころころ代える『代表者隠し』で、誠実に対応していない」と厳しく批判している。元幹部も、この代表者のきわめて頻繁な変更について、(その時点での代表者の自分にあてられた)召喚状を受け取りたくなかったと証言している。こうして、教団は、再び強制執行を妨害した疑いがある。
また、以上の行為は、民事執行法にも違反する疑いがある。
4.【犯罪事実4】関連法人はアレフではないと偽りながら、八潮施設を運営する関連法人への過大な賃料支払いにより、強制執行を妨害し続けている疑いがある
アレフの関連法人である有限会社ブレインマネージメントは、埼玉県八潮市所在の八潮大瀬施設の賃料及び光熱費等を支払うなど同施設を管理し、アレフに転貸している。
しかしながら、2022年5月時点の公安調査庁の調査によれば、有限会社ブレインマネージメントが貸主に支払う同施設の賃料は月額107万2500円であるにもかかわらず(少なくとも2010年5月から2022年8月時点において賃料は同額で推移している)、有限会社ブレインマネージメントに同施設の使用料として、前記107万円強を大幅に上回る毎月125万円(及び光熱費等として毎月約25万円の合計約150万円)を長年にわたって不必要に支払い続け(2022年5月時点)、この賃料の差額を有限会社ブレインマネージメントに不必要に留保している。
そして、2020年以来、その資産を教団の資産ではないと偽り、公安調査庁にも報告せず、強制執行を妨害している。そして、この2022年とは、アレフがブレインマネージメントを含めた関連法人の資産を報告しなくなかった時期と合致する。
5.【犯罪事実5】 麻原の妻・次男が、強制執行が行われることを知りながら、自らが主導するアレフから、絵画使用料の名目で多額の生活資金を自分達個人へ支払って、教団内の資産を不当に教団外に移動させたこと
①2002年12月以来、アレフ教団は、契約に基づいて、麻原の妻に、妻の描いた宗教画の絵画使用料を名目とした月40万円の生活支援金を支払ってきた(この額については、契約書に署名した当時の教団代表の上祐は過剰とも感じたものの、麻原家族を高く位置づける教団の信仰が残っていたため、妻の言い値を受け入れたものである。
この絵画使用料はあくまで名目であり、実質は生活支援金であった。オウム真理教の教えでは、私有財産の放棄(布施)の教えがあり、個人が作成した絵画や著作物を含め、全ては教団に布施したものと位置づけられ、後にも先にも、一個人に絵画や著作物の使用代金を払ったことはなく、妻が描いたシヴァ神の絵画1枚は教団の祭壇に用いられているシヴァ神の絵画ではなく、教団運営に必要不可欠なものではなく、絵画使用料としての40万円の支払いには全く経済合理性はないものであった。
その後、2003年ごろから、上祐らの麻原を相対化する教団改革に対して、麻原を絶対とする三女や妻が教団の裏関与を始めて改革を妨げ、上祐から実権を奪ったが、2006年になって、警察の捜索などで絵画使用料の件が発覚して、同じくアレフに籍を置かずに、側近信者の多額の資金援助を受けていることが発覚した麻原三女らと共に、被害者賠償を軽視し妨げるものとして、被害者関係の方々から強く批判された(読売新聞2006年7月20日夕刊、産経新聞2007年3月20日)。
しかしながら、その打ち切りを主張する上祐らに反して、家族に裏支配された教団は「検討する」とコメントするのみで応じることはなく、上祐はこの問題をメディアに告発し、これを含めた家族の反社会性を一因として、翌2007年にアレフを脱会した。
②それ以降、絵画使用料の支払いの継続の有無は、外部からは確認できなかったものの、2025年7月になって、公安調査庁は、麻原の次男と妻は今現在も、アレフからの「多額」の資金提供で生計を立てていること、上記の絵画使用料が支払われ続けていること、その絵画使用料とは名目に過ぎず、教団からの生活支援金であることは明白と認定して公表した(2025年8月4日付け官報 公安調査庁の第6回の再発防止処分請求書)。
また、同じく2025年7月になって、埼玉県警が今年4月に行った次男と妻の自宅の捜索では、現金数千万円が発見されたことが公表・報道され、一部報道機関は、次男らに自活の気配がないことから、その出所が、以前発覚して、被害者賠償軽視と批判された絵画使用料ではないかと報じられて再び批判されるに至った(参考記事)。
この状況は、アレフが2018年から賠償をせずに、裁判所の賠償命令を受けても賠償に応じずに、強制執行が開始される時期以降については、単に被害者への賠償を軽視した不誠実・理不尽な行為であるだけでなく、賠償のために教団資産を回収する強制執行を妨げる行為である疑いがある。
というのは、同庁によれば、麻原の妻は、「アレフの財産の支出について許可を求められてこれを与えたりする」というアレフ教団の経理上の決済を行う権限を持っていたとも認定されており(前掲官報)、アレフ教団から麻原の妻への資金の移動は、事実上、妻自身の意思で継続されていた疑いが濃厚である。
そして、麻原の妻は、賠償債務を履行せずに強制執行を受ける教団の状況を熟知しているはずであり、さらには、未払いの賠償支払いの対象の一部であるオウム時代の教団内部殺人事件に自分自身が関与しており、その賠償債務の発生の原因に責任がある本人である立場である。
その妻が、強制執行の開始以降も、社会や当局の批判・監視の目を免れるために、教団運営の関与を違法に(団体規制法違反して)隠しながら、絵画使用料を名目とした過剰と思われる生活支援金の支払いを事実上(経費支出を含めてアレフを裏支配する)自らの手で継続し、自らが受け取っていたのである。
そして、2014年以降、次男と交代でアレフ教団の裏関与から離れた三女・長男らとさえ異なって、前記報道のように、自活努力の気配も見られず、当初の40万円から十分な減額があったとの情報もない。仮に絵画使用料が40万円のまま継続されていれば、強制執行の元となる裁判が開始され、教団が支払いを停止した2018年から(公安調査庁が支払い継続を認定した)今年2025年7月までの間には、合計3500万円以上に上ると推計され、最初に発覚して社会の批判を浴びた2006年からの19年間では9000万円以上に上ることになる(さらに、絵画使用料以外に教団・信者から資金援助・布施がないということもまた非常に考えにくい)。
なお、公安調査庁が、麻原の妻・次男を教団の構成員として公に認定したのは本年・2025年7月であり、その自宅を教団施設として初めて検査をしたのは同年3月、それを契機に強制捜査で大金が発見されたのは同年4月であるため、それまでの間は、強制執行を行う支援機構から見れば、麻原の妻・次男の自宅は、強制執行の対象とするのは困難であり、教団内から教団外に資金が移動した結果となっている。
こうして、妻・次男は、強制執行の対象となるべき教団の資産を意図して極めて身勝手・不当に、教団の外(=自分の個人資産)に移転して、その執行を妨害したという疑いがある。
6.その他の犯罪事実
上記の5つの被疑事実以外にも、公安調査庁によれば、出家信者への個人給与を不必要に急増させ、教団の簿外の資産を増やしており、強制執行を妨害している可能性がある。
公安調査庁によれば、教団は、被害者支援機構が賠償命令を求めた裁判を提起すると、その関連事業体の出家信者に支払う給与について、2018年(平成30年)から2019年(令和元年)にかけて、約4300万円から約1億2400万円にまで急激に増加させ、2021年(令和3年)には、さらに約1億8300万円にまで増額させるに至った。
この2018年は、教団を相手取って被害者支援機構の賠償命令を求める裁判を東京地裁に提起した時期である。2021年は上記の通り、その2月に出家信者の預貯金口座が差し押さえられた時期である。しかし、公安調査庁も指摘するように、これは形式的なものであり、出家信者は、全財産を教団に布施するという教えに基づいて、個人資産は認められておらず、経理担当者から現金で給料を受け取ると即座に、教団に布施をする仕組みになっている。
その際に、公安調査庁の調査によって、「家計」と称するアレフの簿外の会計に納められる場合があるが、この「家計」も、実際には個人が管理するものではなく、教団が管理するものであって(主に出家信者の日常生活の費用の支払いを行う資金と位置づけられる)、実質的にアレフの資産であることが判明しているが、公安調査庁には報告されないものである。よって、上記のように、個人の給与を不必要に急増させることは、教団の表向きの資産を不必要に急減させて、強制執行をより困難なものとすることは明らかである。
さらに、元幹部の証言によれば、急激に給料を増額した時期において、少なくとも一部の給与に関しては、その支給の事実が、本人には全く知らされておらず、経理担当者が、違法に管理していると思われる事例が発見された。すなわち、上記に述べた儀式的な現金給与の受け渡しと直後の教団への布施の儀式や、給与明細書の発行も行われていない事例である。これは、法的には業務上横領罪に当たる疑いがあるとともに、ある意味で裏金作りともいうべきもので、違法に教団の簿外に出して、強制執行をより困難にするものである疑いがある。