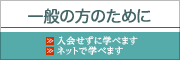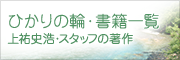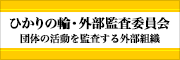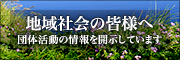2024年 GWセミナー特別教本「悟りの心理学:人類の心理的進化の可能性 脳科学が説く新たな幸福の価値観」
(2025年4月28日)
2024年 GWセミナー特別教本「悟りの心理学:人類の心理的進化の可能性 脳科学が説く新たな幸福の価値観」
第2章 脳科学が説く感情と心身の健康との深い関係
1.脳科学が解明する感情と健康との関係
最近の脳科学の著しい発達の中で、感情と心身の健康との関係が、科学的に解明されてきた。そこでは、後に詳しく述べるが、脳の組織に加えて、脳内物質・脳内神経伝達物質・ホルモンなどといわれるさまざまな物質と、その作用が発見され、確認されている。
例えば、"癒しのホルモン"のエンドルフィン、"親切と安心のホルモン"のオキシトシン、"闘争と逃走のホルモン"のアドレナリン、"ストレスのホルモン"のコルチゾールや、さらには、交感神経と副交感神経からなる自律神経の働きなどが関係してくることがわかっている。本稿では、これについて解説したい。
2.思い込み効果には科学的な根拠がある
病気に関して、薬の効き目に対する肯定的な思い込みが、心身の状態を良くし(プラセボ効果)、逆に、否定的な思い込みが、心身の状態を悪くするということがある(ノセボ効果)。例えば、患者に「薬である」と偽って、単なる水を飲ませると、病気の症状が緩和するなどである。
この効果は、以前は、単なる思い込みによる効果だと考えられていた(すなわち、実際には体の状態は改善していないが、患者が改善したと思い込んでいる)。しかし、最近の研究では、プラセボ効果が起こる場合は、オキシトシン、内因性オピオイド、ドーパミン、バソプレシンなどの分泌が観察されているという。
これらは高い鎮痛効果があるため、痛みや苦痛を緩和するという効果が実際に表れるのだという。「これを飲めば治る」などという、「安心」や「期待」の感情は、単なる思い込みではなく、病気を実際に緩和するホルモンや物質の分泌を促し、実際に、免疫力・治癒力を高めているのだという。
一方、ノセボ効果とは、薬に対する不信感が強いと副作用の出現率がアップし、さらには、医者に対する不信感が強いと薬の効果が減じるという。そのため、同じ薬を飲むのなら、「必ず効く」と思って飲むべきだと主張する医師もいるという。
だとすれば、プラセボ効果やノセボ効果は、新型コロナのワクチンにも作用するのだろうか。ワクチンを強く肯定している人の方が、その効果が高く表れ(免疫力が高まり)、副作用・副反応が少ないという可能性があるかもしれない。
3.闘う意識が分泌させるアドレナリンやコルチゾール
人の脳は、何かの脅威を感じると、それに対して、闘うか逃げるか(闘争か逃走か)という反応をするが、この際に、短期的には、副腎髄質からアドレナリンが分泌され、長期的には、副腎皮質からコルチゾールなどのホルモンが分泌されるという。
アドレナリンは、心拍や血圧、呼吸数の増大、骨格筋への血流の増加、発汗などの反応を引き起こし、身体機能をアップさせ、闘う状態をサポートする。問題は、これが長時間ないしは1日に何度も繰り返されると、①身体機能を酷使することになり、②心拍・血圧の上昇から血管の収縮や血流の悪化が生じ、全身の細胞に栄養が行きわたらなくなる。
さらに、アドレナリンは血小板の働きを活性化させて、血液が固まりやすくなる作用があるため、それが分泌過剰となると、③血液がドロドロの状態となって血管が老化し、心筋梗塞や脳卒中などの心血管系疾患になるリスクを高めるという。
アドレナリンは、闘争や逃走に関係すると述べたが、より具体的には、不安、恐怖、闘争、怒り、興奮といった感情を抱いている時に分泌されている。まとめて言えば、何かの存在に対して嫌悪し、その受け入れを拒絶し、それを排除しようとする感情である。
本来は、こうした感情は、自分の身を守るために必要なものとして存在していると解釈できる。例えば、原始人の脳は、野獣を見た時にアドレナリンが出て、それによって自分の身を守ってきた。
しかし、現代の人々に関しては、こうした感情が、不必要に過剰となっている問題が指摘されている。例えば、人から少しでも批判されると、それを受け入れられずに強い拒絶感が生じ、恐怖・不安を感じるなどである。そういう場合は、アドレナリンの分泌過剰となって、逆に、心身を痛めてしまうことになる。
4.現代人の健康を損なう交感神経の過剰優位の問題
他者に対する受け入れの拒絶、恐怖、不安、闘争、怒りなどの感情が強すぎると、交感神経と副交感神経からなる自律神経のうち、交感神経が過剰に優位となる問題が生じる。交感神経は、活動・興奮をもたらし、いわゆる昼の神経であり、心拍数、呼吸数、体温を上昇させ、活発な活動を支える。
副交感神経は、休息・睡眠・リラックス・回復をもたらす、いわゆる夜の神経であり、(夜間を中心に)睡眠を誘導し、身体を回復させ、細胞を修復し、免疫力をアップする。よって、昼は交感神経、夜は副交感神経が、交互に優位になることが健康な状態である。
しかし、昼間に嫌なことがあり、夜になっても、その不安・恐怖・怒り・嫌悪といった感情が残ると、アドレナリンが分泌され、交感神経優位の状態が続き、睡眠を誘導する副交感神経の働きを妨げて、眠れなくなってしまい、不眠の症状が出てくる。
そして、不眠になると、がんのリスクは6倍、脳卒中は4倍、心筋梗塞は3倍、高血圧は2倍、糖尿病は3倍となるという。その意味では、夜間におけるこうした感情をコントロールして睡眠を確保することが、健康の1つの鍵となる。
5.継続的なストレスはコルチゾール過剰の状態をもたらす
ストレスは、人生のスパイスともいうべきものであって、必ずしも悪いものではない。しかし、私たちの身体の作りは、短期間であれば大きなストレスに耐えられるが、長期にわたる継続的なストレスは、心身をむしばむという。
例えば、毎日過度に頑張ることを、長期的に継続的に続ける人の場合は、前に述べた通り、副腎皮質からコルチゾールというホルモンが分泌される。このコルチゾールは、身体を活発に動かし、生命の維持に必要な活動を担っており、気つけ薬のようなホルモンである。
主に朝に出るので、目覚めのホルモンともいえるかもしれない。具体的には、血糖値・血圧を高め、エネルギーを生み出し、精神的・肉体的なストレスに対抗し、炎症・アレルギーを抑える(抗炎症効果)。よって、コルチゾールの分泌が不足する病気がある。
しかし、先ほど述べた長期的・継続的で慢性的なストレスが続くと、コルチゾールの分泌が過剰となり、夜間も、その血中濃度が高止まりする。すると、夜間も身体が休まらないことになる。また、コルチゾールには、免疫抑制作用もあるので、免疫力が低下する。
さらに(夜間の)コルチゾールの高(こう)値(ち)が続くと、高血圧・糖尿病・感染症などの原因となり、脳の海馬の萎縮が起こるために、記憶力も低下する。そして、うつ病や各種メンタル疾患の患者においても、夜間のコルチゾールの高値が観察されており、メンタル疾患の原因にもなる。こうして、慢性的なストレスは、各種の病気の原因となり、病気の予防のための免疫力、病気を治す自然治癒力の低下をもたらすとされる。
6.不安や恐怖は脳の扁桃体の異常興奮
人は、強い不安や恐怖に直面すると、大脳辺(へん)縁(えん)系の「扁桃体」が興奮し、ノルアドレナリンという脳内物質を分泌するという。これはアドレナリンと非常に似通っており、闘争か逃走かの行動をもたらす。
ノルアドレナリンは、脳と神経系に働き、闘うか逃げるかの選択・決断を促し、アドレナリンは、脳以外の心臓・筋肉・各臓器に働き、闘うか逃げるかの状態に体をもっていく。双方とも、(危険に対する)不安・恐怖といった感情に関連して分泌され、怒りや興奮が高まると、アドレナリンは、より分泌されるという。
不安や恐怖にとらわれると、人は、それから反射的に逃げ出したくなるが、この反射的に発動する感情のシステムを、情動反射と呼ぶ。情動反射は、前に述べた扁桃体が司り、条件反射のようなもので、知性・理性によってコントロールされない原始的なシステムであり、魚類や爬虫類にも備わっているという。
これに対して、理性的・論理的な判断は、大脳新皮質の前頭(ぜんとう)前野(ぜんや)が司り、これが通常の私たちの脳の主導権を握って支配している。しかし、危機的な緊急事態に直面した際は、のんびり考えている暇はなく、前頭前野の思考や理性が働く前に、先ほど述べた扁桃体などによる情動反射が、心と身体を瞬時に支配する。その後、危機が去れば、前頭前野が支配権を取り戻し、扁桃体は沈静して不安は解消する。
そして、情動反射の中枢である扁桃体は、暴れ馬のような面があり、理性・論理的思考を司る前頭前野は、その暴れ馬をコントロールする手綱(たづな)のようなものであるが、不安が強い状態では、その手綱が外れて、扁桃体が暴走する面があるのである。
7.扁桃体の暴走を止めるには?
野獣に襲われるなどの危機的な緊急事態においては、扁桃体を中枢とする情動反射が必要である。しかし、そうした緊急対応が必要でないときも、不安や恐怖によって扁桃体が暴走することが、人間には少なからず起こる。そして、現代社会では、慢性的なストレス・不安・恐怖・怒りの感情によって、この問題が増えている可能性があると思う。
これは、感情・情動が、理性・論理的思考の制御を受けずに、暴走して冷静さを欠いた状態であるから、その感情のままに行動すると、後から後悔する行動をとることが多い。よって、緊急対応が必要でない時にも、不安・恐怖にかられた時には、それを自分の本当の考えだと思って、その感情のままにすぐさま行動するのではなく、時間を置くことが望ましい。時間を置くことによって、待つことによって、扁桃体の興奮による情動反射が静まってくるからである。
また、最近の脳科学研究によれば、不安・恐怖をもたらす扁桃体の興奮を抑制するには、言語情報を入れることが有効であることがわかっている。例えば、「少し待ってみよう」と、言葉にして声に出して言うことなどによって、扁桃体の興奮を抑制することができるという。そして、言語情報を脳に入れるには、「話す・聞く・読む・書く」の方法がある。
第一に、言葉に出して言うことである。独り言でもよいので「大丈夫」などといったポジティブな言葉を声に出す方法がある。言葉にせずに、黙って感情に対して我慢をしていると、逆効果という見解がある。
第二に、他人に話すことである。(落ち着いている)友人や知人に、自分の心配・不安を話すこと。話すだけでも、不安・ストレスを和らげる効果があるといわれる。
ここで、単に、自分の不安を話す相手ではなく、不安を解決する方法を相談できる人(専門家など)がいれば、なおのことよいだろう。他人に相談しても何も解決しないという人もいるかもしれないが、この場合も、相談する行為によって、不安の感情が言葉に置換されて、扁桃体が抑制され、不安が解消するというメリットがある。そして、前頭前野による理性的・合理的な問題解決のための判断がしやすくなるのである。
第三に、書くことである。自分の不安などの感情を、ノートに書いて吐き出すなど。この応用として、日記を書くことがある(心理学では日記療法というものがあるという)。
8.他者の拒絶・孤独感がもたらす心身の不健康
何らかの問題のために、恐怖や不安といった感情が強く表れると、他者の受け入れを拒絶し、心を閉ざして、孤独な状態に至ることがある。そして、それが日常生活で慢性的になり、慢性的な孤独感が生じると、深刻な影響があるという。
シカゴ大学の心理学者のジョン・カシオポ氏によれば、慢性的な孤独感は、人を不安定にさせ、他者に対する被害観を抱かせ、自虐的・自滅的な思考や行動に陥らせるという。さらに、孤独は、身体にも大きな影響を与え、脳血管、循環器、がん、呼吸器や胃腸の疾患で死ぬリスクを高めて、高血圧や肥満、運動不足、喫煙などに匹敵する悪影響があるという。
米オハイオ大学の研究では、孤独感は、免疫力低下と関係があり、身体の不調を招く原因となることを明らかにしたという。米プリガムヤング大学の研究によると、社会的なつながりを持たない人は、持つ人に比べて、早期死亡リスクが50%高いという。
孤独の健康への悪影響は、1日15本の喫煙に匹敵し、運動不足や肥満の3倍であり、うつ病のリスクは2.7倍、アルツハイマー病のリスクを2.1倍増やすという。免疫力を低下させ、多くの心身の病気のリスクを増やすのである。
9.悪口や過剰な怒りも健康を損なう:人を呪わば穴二つ
過剰な恐怖・不安・怒りといった、他者の受け入れを拒絶する心の働きが強くなると、それに伴い、悪口が多くなると思われる。しかし、精神科医の樺(かば)沢(さわ)紫(し)苑(おん)氏は、「病気の治らない患者さんの特徴を一つ言えと言われたら、私は『悪口が多い』を挙げます。本人は悪口を言うことでストレス発散が出来ていると思っているかもしれませんが、これは完全に間違いです。悪口は病気を悪化させるし、そもそも病気の原因にもなるのです」と言う。
フィンランドの脳神経学者のトルパネン博士の研究チームは、1449人を調査して、悪口や批判が多い人は、そうでない人に比べて、認知症になる危険性が、3倍も高いことがわかったという。他の研究によれば、悪口の多い人は、そうでない人に比べて、寿命が約5年も短いというものもあるという。
この1つの原因として、悪口を言うと、ストレスホルモンであるコルチゾールが分泌される。よって、頻繁に悪口を言う悪習慣のために、長期にコルチゾールの高値が続くとするならば、前に述べた通り、免疫力が低下し、さまざまな病気の原因になると思われる。
そして、扁桃体などの大脳辺縁系といわれる脳の部分は、主語が理解できないために、自分の他人への悪口も、他人の自分への悪口も、区別することができず、悪口を言っても、悪口を言われた時と同じように、扁桃体は興奮し、不安と恐怖を感じるという。すなわち、悪口を言うと、悪口を言われた場合と同じストレスが生じるということになる。
さらに、他人への悪口・怒りが強い人は、それとセットで、自分への怒り・自己嫌悪も強い傾向がある。何かを理由として、他人を強く否定するならば、その他人と同じ要素を自分に見た時には、自分を強く否定することになる。
また、自分と関係がある他人を否定するならば、その他人と関係を持った自分の過去を後悔して、自分を否定することが少なくなく、言い換えれば、自分と他人(の否定)は、完全に区別できないのである。
そして、前に述べたように、怒りは、アドレナリンが大量に分泌されている状態であるから、これが長期にわたって分泌される状況となると、高血圧、動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中などの心血管系疾患になるリスクを大幅に高めるのだという。ある研究では、激しく怒った後には、心筋梗塞や心臓発作を起こす危険性が4.7倍に上昇するという。
また、ある研究データによれば、一度怒って自律神経が乱れると、それが正常化するには、3時間程度を要するという。アドレナリンの分泌が長期で続くと、前に述べた通り、コルチゾールも過剰に分泌されるようになり、記憶力の低下、免疫力の低下、体と心の双方の健康を損なうことになる。こうして、昔から「人を呪わば穴二つ」というが、この諺には、今や科学的な根拠があるということができるのではないだろうか。
10.医学的な視点からの怒りの制御
ここでは、前出の精神科医の樺沢紫苑氏が提案する、怒りの制御の方法を紹介する。なお、私たちがこれまでに学んできた仏教思想には、人間の怒りを含めた煩悩の心理の根本的な洞察に基づいて、怒りを制御するさまざまな修行法が説かれている。同氏の見解は、その仏教の思想・瞑想と一致する部分も一部にあるが、一致しない部分もあるので、参考として紹介したい。
第一に、同氏は、吐く息を長くした深呼吸を提唱する。それは、腹式呼吸による20秒の深呼吸であり、まず、5秒かけてゆっくり鼻から息を吸い、次に、15秒かけて口から息をすべて吐き切り、これを3回繰り返すというものである(合計で1分)。
これは、自律神経の権威である順天堂大学の小林弘幸教授が提唱する、長生き呼吸法に通じる。小林氏の呼吸法は、4秒で鼻から吸い、8秒で口から出すものであり、いずれも吐く息(呼気)の長い深呼吸である。こうすることで、自律神経の中の副交感神経が活性化し、リラクセーションが促進される。なお、樺沢氏によれば、吸気と呼気が1対1の場合は、逆に、交感神経が活性化してしまうので、逆効果だという。
次に、同氏は、怒りが生じてカッとした時には、ゆっくり話すことを勧める。怒っている人は、ほとんど早口であり、逆に、ゆっくり話すように努めると、気分が落ち着くという。これは、人間は、興奮すると早口になり、交感神経が優位になり、さらに興奮が進むからだという。
第三に、怒りをノートに書き出してみることである。前に述べたように、怒りを悪口として他人にぶつけるのはよくない一方で、無理に我慢してため込むのもよくない場合には、その怒りの内容をノートに書き出すと、誰にも迷惑をかけることなく、すっきりするという。
しかし、これだけを繰り返すと、ネガティブな思考パターン・記憶が強化されてしまうので、それを防ぐために、しばらくした後で、第三者の客観的な視点から、ノートに書き出された自分の怒りの内容を見て、賢者の視点から、自分自身への助言を書くのである。自分のネガティブな感情をノートの左側に書いて、右側に、それに対する賢者の見解を書くとよいかもしれない。
最後に、他人への怒り・攻撃的な行為の背景には、なにかしらの不安や恐怖があり、その際は、扁桃体の興奮が生じていることを知っておくことである。そう知っておくことで、不安や恐怖から怒りが生じた時に、冷静に対処しやすくなるという。
11.笑いがもたらす心身への望ましい効果
「人を呪わば穴二つ」とともに、「笑う門には福来る」という諺がある。これもまた、最近は、科学的に証明されつつある。
笑うことで、①幸福の神経伝達物質とされるドーパミン、②鎮痛効果があり快楽物質(脳内麻薬)ともいわれるエンドルフィン、③精神安定をもたらすセロトニン、④安心をもたらす効果があるオキシトシンといった、心身に良い脳内物質が分泌されるという。
その逆に、コルチゾールのようなストレスホルモンが抑制され、ストレスが緩和され、結果として、笑いによって、免疫力が向上し、痛みが緩和され、各種疾患の改善をもたらし、記憶力が改善するという。
加えて、当然のことであるが、笑顔の人の方が、他人との人間関係もうまくいく。笑顔により、自分だけでなく、他人にもオキシトシンが分泌され、他人を癒すことができるという。
なお、意識的に笑顔を増やすこと、すなわち、作り笑顔であったり、割り箸を口にくわえるなど口角を物理的に上げたりするだけの場合でも、前出の幸福をもたらす脳内物質の分泌が確認されているという(ただし、無理にやれば効果がないという報告もある)。
12.慈善・利他・感謝は心身を健康にする
一般に、ヘルパーズ・ハイという言葉があるが、人助けをする人は、非常に活動的で、テンションが高いという。メアリー・メリル博士の研究は、慈善活動をする人は、そうでない人に比べ、モチベーションが高く、活動的で、達成感や幸福感を強く感じ、心臓疾患の罹患率が低く、平均寿命が長く、健康で長生きしていることを明らかにしたという。
英国のエクセター大学の研究では、慈善活動をする人の死亡リスクは、しない人に比べて20%低いという科学的な根拠を見出したという。また、抑うつレベルが低く、生活満足度、幸福度も高いという。
米テキサス大学の3617人を対象とした調査では、慈善活動をした人は、うつ状態が少なく、その傾向は65歳以上でさらに顕著だったという。米ミシガン大学の研究でも、死亡リスクが低いという結果が得られているという。
そして、こうした慈善活動・ボランティア活動をする人たちの特徴として、次の項目で述べる通り、感謝が多いという。
また、感謝の重要性を示す研究結果が、多数報告されている。感謝する人は、病気になりにくく、長生きし、病気の回復が早いなどである。感謝とうつの関係の研究によれば、うつ傾向の強い人はあまり感謝せず、うつ傾向が弱い人は感謝する傾向が強いという。
カリフォルニアのサンルイス病院の研究によると、明確な原因がないのに痛みが続く患者に、深く感謝する瞑想を、4週間実践してもらったところ、明らかに痛みが減ったという。また、感謝の実践によって、幸福感が増す、病気の症状が少なくなる、より運動をして活動的になるという研究結果がある。さらに、同じ研究結果の中で、より人助けをするようになり、他人からも「優しくなった」と言われるようになったという。
こうして、感謝と親切・利他には関係があるようだが、これは、すでに第1章で述べたように、感謝の心が深まれば、当然、恩返しとしての利他・親切の実践に結び付くことが考えられる。
13.エンドルフィンとオキシトシン
感謝によって分泌される重要な物質として、エンドルフィンとオキシトシンがある。エンドルフィンは、脳内麻薬ともいわれ、モルフィネの6.5倍ほどの鎮痛効果がある。これは、感謝される時、感謝する時に分泌されるという。走っている時、激痛を感じている時などにも分泌されるが、そうした場合と比較しても、感謝される時の分泌量が圧倒的に多いという。
そして、エンドルフィンは、免疫力や身体の修復力を高め、がんとも戦う免疫機構のNK活性を高め、抗がん作用も確認されており、さらには活性酸素を撃退し、体調・健康の改善、若さを保つという。その意味で、エンドルフィンは、心身の癒しのホルモンである。
オキシトシンは、親切・感謝・思いやり・慈しみ・赦しといった感情や行為と関連して分泌され、親切のホルモンとも呼ばれ、ストレスが解消し、幸福感が増え、血圧の上昇を抑制し、心臓機能を改善し、長寿になるといった効果があるという。
また、オキシトシンは、ドイツのユスタスリービッヒ大学の研究において、不安の原因である扁(へん)桃体(とうたい)の興奮を鎮静化し、さらには扁桃体が脳幹に送る緊急警報の信号を低減することが発見されたという。こうしてオキシトシンは、安心をもたらすホルモンということができるだろう。また、交感神経にブレーキをかけて、副交感神経を活性化する作用もあり、そのため、免疫力の向上、休息と回復を促進する効能もあるという。
14.脳科学から見た幸福と仏教思想の類似性
最先端の脳科学が示す、これからの幸福になる生き方を学ぶと、それが仏教的な思想における幸福観と重なる点が多い。第一の共通点は、自分だけの利己的な幸福を求めるのではなく、自他双方の幸福、利他的な幸福を求めることの重要性である。
脳科学から見て、他に感謝したり、他を利する気持ちや行動は、自分を利するものであることが確認されたが、仏教の教えでも、感謝と慈悲は、仏教で最高の生き方とされる菩薩道の重要な要素である。
菩薩道とは、すべての衆生を(今の自分を育んだ)恩人と見て感謝し、その恩に報いるために、さまざまに苦しむ衆生すべてに対して、慈悲の心を持って済度するという生き方であり、感謝と慈悲が、重要な実践上の柱となっている。脳科学的に言えば、これは、救済される衆生に加え、菩薩道を行う者自身が幸福になる生き方であるということになる。
ここで重要なことは、最先端の脳科学に基づく幸福観と、仏教思想の幸福観の共通点として、利他は真の利己という視点があることである。利他の心や行為は、他を利するとともに、それを実践する本人こそを利するということである。これは、自と他の幸福は一体であり、自他双方の幸福を求めることこそが、真の幸福の道であるという考え方に結び付く。
フランスのマクロン大統領の生みの親ともいわれるヨーロッパ有数の識者であるジャック・アタリ氏などが、「利他こそ最も賢明な利己である」という思想を提唱しているが、仏教を含む伝統的な宗教思想に加えて、脳科学という最先端の科学が、それを裏付ける時代となった。
15.喜びの神経伝達物質「ドーパミン」とその裏の問題点
さて、エンドルフィンやオキシトシンとともに、喜び・幸福感を与える神経伝達物質であるドーパミンについて述べたい。これについては、第3章で改めて詳しく述べるが、中枢神経系に存在し、先ほど述べた怒りのホルモンのアドレナリン、ノルアドレナリンの前駆体(ぜんくたい)でもあるとされる。
そして、これは、何かを獲得・達成したときの喜び・快感を与え、それに基づく意欲を生み出す。ただし、感謝によって出るエンドルフィン、愛情・慈しみによって出るオキシトシンの明るい温かい気持ちをもたらす幸福感と異なって、興奮を伴う喜び・歓喜という特徴があると思われる。
原始的な状況でいえば、例えば、その日に生き残るための獲物を苦労して獲得したときに生じる喜び・歓喜の感情である。この状況では、アドレナリンも出ている。小動物や草食動物が狩猟の対象である場合は、それは直ちに自分の身の脅威にはならないが、生き残るために動物を捕食することを迫られているわけだから、生き残りのための戦い(生存競争)の中にいるわけで、体はアドレナリンが分泌されて戦闘モードに入るわけである。
こうして、他者へのポジティブな気持ちの際に出るエンドルフィンやオキシトシンと異なって、ドーパミンは、他者に勝利した際の歓喜のためにも分泌されるということである。獲物を獲得するとは、自分には幸福だが、獲物側には死・不幸を意味するし、戦争による自己の勝利と生き残りは、他人の敗北と死を意味するものである。
さて、ドーパミンの話に戻すと、ドーパミンは、獲得・達成したときに快感を与えるだけでなく、その先に獲得する可能性があるときも、分泌されて快感を与える。それが獲得・達成しようとする意欲を形成する。よって獲得に加えて、さまざまな事柄に関する意欲の形成に関する神経伝達物質である。
ところが、ドーパミンには、一つ重要な特性がある。それは、同じものが苦労なく平然と獲得されるような状況が続くと、すなわち同じ刺激が続くと、徐々に分泌されにくくなり、喜びを感じられなくなるということである。そのため、ドーパミンが出て喜びを感じるためには、より強い新しい刺激が必要となる。すなわち、以前よりもっと多く、もっと良いものを獲得しなければ、ドーパミンが出ないのである。
これが、人の欲求は際限がないという事実の背景の1つではないかと思われる。何かを新たに得た場合はうれしいが、それがそのまま続くならば、それは当然のものと感じられて喜びではなくなり、それ以上を求めるようになる。その一方で、得たものに関しては、それにとらわれてしまい、それを失うと苦しみを感じる。
例えれば、給料が15万円から20万円に増えた時はうれしいが、その時の喜びは長くは続かず、「もっと欲しい」と思うが、そのままずっと20万円であれば、自分は頭打ちであると苦しむ。さらに、仮に20万円が15万円に下がれば大変苦しむ。20万円に上がる前は、15万円でもそれなりにやっていたにもかかわらずである。
16.ドーパミンがもたらす「とらわれ」「依存症」
こうして、ドーパミンは一種のとらわれ、それなしではいられない中毒症状的な状態を作り出す面がある。実際に、薬物を摂取して感じる快感は、回を重ねるごとに減少し、摂取する量を増やす誘惑にかられるのも、このドーパミン神経回路の特性である。
そして、過剰な飲酒・過食・買い物・ギャンブルに対して、足るを知らずにのめり込んでいくのも同様である。その意味でドーパミンは、時に、人が何かに過剰にのめり込む状況をもたらす面がある。
そして、もっと求めたとしても、かなわない場合が多い一つの背景には、自分だけではなく、皆がもっと求めるために、奪い合いが生じるからにほかならない。よって、もっと得ることはおろか、逆に他人に奪われて、前よりも減る場合さえある。この場合、他へのやっかみ・妬み・憎しみ・恨み・怒りが生じて、苦しむことになる。それが、場合によっては、互いの生死をかけた闘争・戦争の原因にもなる。
このドーパミンによる際限ない欲求の拡大は、他人との闘争・競争の勝利、名誉・地位・権力・支配の欲求にも当てはまり、それらの追求を、際限のないものにする可能性がある。よって、このドーパミン神経回路の働きは、ある程度制御しなければならないという面があるが、これについては、また後で述べることにする。
17.過剰な勝利・優位の欲求の大きな弊害
ところが、他との競争で勝利しようとする欲求、「他と比較して優位になりたい」という欲求は、それが行きすぎると、特に現代の社会においては、幸福よりも、逆に不幸をもたらす面が目立ってきたという重要な事実が、脳科学の視点から指摘されている。それに関わってくるのは、先ほど述べたアドレナリンや、ストレスホルモンといわれるコルチゾールである。
ただし、前もって結論をいうならば、これは、優れたスポーツ選手がそうであるように、競争の相手を自分の幸福を奪う「敵」とは見ずに、切磋琢磨して互いに成長し合う「友」と見る場合には、当てはまらない。その場合は、人は、競争の勝利を絶対としてはおらず、勝ったり負けたりしながら、切磋琢磨して皆で成長するシステムだと考え、競争相手を自分の助力者・友と見る。
勝利を絶対だと考えると、強い競争相手は、自分の幸福を妨害する敵であり、悪魔のように見えて、憎しみ、妬みの対象となる。しかし、(共に)成長することが目的の場合は、競争相手は強力な方がよく、自分の成長=幸福の大きな助力者、恩人、教師・導き手(神・仏)と見えるだろう。
前者の勝利絶対の場合は、さまざまな心身の問題・人間関係の問題が生じる。競争の勝利を絶対として、自分と他人を比較して他に優位に立つことを強く望み、劣っていることを強く嫌がる場合は、現代人にも非常に多い。いや、競争社会の現代社会こそが、他の時代に比較しても、自と他の優劣の比較に、より深く陥っているのではないかとも思わせる。
結果として、自己嫌悪・コンプレックス・妬みや、他者の自分の扱いへの不満・怒りなどが、相当に現代人の心には渦巻いている。勝てないからあらゆる競争には参加せず、他人と交流するとコンプレックスを感じるため交流せず、社会から引きこもる(これを心理学では「劣等コンプレックス」の心理状態などということがある)。そして、孤独に苦しむ。「他人より劣っているばかりの自分は、生きていてもちっとも楽しくないし、生きる価値を感じない」と思い、生きがいを喪失する。うつなどの精神疾患に至る。自死ないしは孤独死に至る。
また、自分が劣っているというコンプレックスに対して、引きこもるのではなく、それを紛らわすために、自分に実力がないという現実を受け入れずに、自分に対する他者・社会の扱いが不当・不合理だと思い込む。そして、他者に攻撃的で、独善的、被害妄想的な意識・言動に陥る(これを心理学では「優越コンプレックス」という)。ことさら他人の悪口を言って貶めて、自分以下の存在と見ようとする。問題が起こる度に、他に責任転換をする。時には独善的な視点から、他人には有難迷惑なことをする。不正を行ってまで、競争で他者に自分が勝ったように見せかける。そして、昨今大きな問題となった電車などでの無差別大量殺人も、このタイプの、社会全体や勝ち組への不満・怒り(逆恨み)に起因するとされる。
話を元に戻せば、他者が本当に自分の存在にとって脅威であるならば、それに対してアドレナリン・ノルアドレナリンが分泌されて、戦闘モードに入り、戦うか逃げるかの行動をとることは必要である。しかし、実際にはそうではないのに、勝利ばかりを絶対とする競争や、他との過剰な優劣の比較などによって、いろいろな他人を、自分の幸福を妨害する敵とばかり見るようになり、敵意・悪意・怒り・妬み・憎しみ・恐怖・不安・自己嫌悪・コンプレックスといったネガティブな感情を抱くならば、それは心身に逆効果になる。
前に述べたように、アドレナリンが、体を酷使することになり、高血圧・高血糖(糖尿病)・脳血管・心臓などの疾患のリスクを高める。例えば、高齢者が、瞬間湯沸かし器のように怒った後に、脳血管障害で死亡するリスクが高いことは、よく知られている。
なお、アドレナリンが、本当の危機に対して一時的に出ることには、人間の体は耐えられるという。頻繁に出る、絶えず出ることになると、人間の体は耐えられない。わかりやすく言い直すと、人間の体は、一時的には強いストレスには耐えやすいが、持続的なストレスには耐えにくいという。
そして、ネガティブな感情が継続的になると、ストレスホルモンのコルチゾールの分泌が過剰となる。こうなると、免疫力が低下し、記憶を司る脳の海馬が萎縮して、知能が低下する。うつ病などの精神疾患のリスクも増大する(うつ病の人はコルチゾールの値が高いという)。また、慢性疾患のリスクの増大ももたらすという。
加えて、自律神経の交感神経が過剰に優位となる。すると、緊張・不安などによって、不眠症や、それによる生活習慣病のリスクが増大する。また、免疫力・細胞の再生力が低下して病弱になる。精神的には、リラクセーションができず、十分に休息できなくなる。
よって、他を敵視する怒り・恐怖・不安といった感情は、必要な場合に制御し、自分の心身の健康・知能・人間関係が不要に損なわれないようにする必要があるということができるだろう。