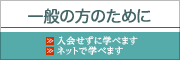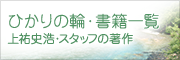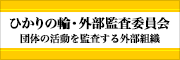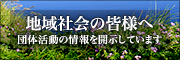2022年 GWセミナー特別教本「瞑想法の総合解説 心身の健康から悟りの境地まで」
(2025年4月28日)
2022年 GWセミナー特別教本「瞑想法の総合解説 心身の健康から悟りの境地まで」
第1章 瞑想とは何か
1.はじめに
瞑想という言葉が、最近あちこちで聞かれるようになったが、その定まった定義はなく、非常に広い概念である。例えば、心を静めて無心になること、何も考えずリラックスすること、心を静めて神に祈ること、何かに心を集中させること、目を閉じて深く静かに思いをめぐらすこと、などと考えられている。
瞑想は、宗教との結びつきが深く、各宗教・宗派によって、さまざまなものがある。よって、単に心身の静寂を取り戻すために行う健康法のようなものから、絶対神信仰の宗教において絶対者(神)をありありと体感したり、仏教が説く究極の智慧を得たりするようなものまである。加えて、現代では、心身の健康、心理療法、自己開発・自己向上といった世俗的な目的をもって、さまざまな瞑想が行われている。
2.さまざまな形をとる瞑想
瞑想において、どのような体の使い方をとるかにも、定まった形がない。日本人になじみが深い、静かに座って行うもの(座禅)、立ちながら行う瞑想(立禅)、歩きながら行う瞑想(歩行禅・歩行瞑想)などがある。
また、一部のヨーガのように、さまざまな体位を取るもの(アーサナ〈体位法〉)も本質的には瞑想と考えられるし、ヨーガや仏教(特に密教)の一部にある、特定の音を繰り返し唱える瞑想(マントラ・真言瞑想)、さらには、集団で母音を低い声で続けて発する倍音(ばいおん)声明(しょうみょう)も瞑想と位置づけられることがある。
さらには、太極拳や、スーフィーの旋回舞踊ダーヴィッシュ・ダンスのように動きながら行うものを含むという見解もあり、武道や舞踊の修行・実践や滝行に瞑想を見出す人もいる。こうして、瞑想時の体の使い方から見ても、さまざまなスタイルのものが存在する。
また、精神の集中の仕方の視点からも、一点に集中するもの(ヨーガのダーラナー(凝(ぎょう)念(ねん)))、集中範囲が広いもの(ヨーガのディアーナ(静慮(じょうりょ))や仏教のヴィパッサナー)、特定の対象に注意を向けないもの(禅の無(む)念(ねん)無(む)想(そう)の瞑想)、さらには対象と自分の意識が一体化する究極の集中状態(ヨーガのサマーディ(定(じょう)))がある。
また、瞑想時の思索の視点からは、特定の主題に関して、いわゆる深く正しく考える(ないしは観想する)瞑想もあれば(いわゆるmeditationといわれるものはこのタイプとも思われる)、思索・省察することをしない(ないしは超越した)瞑想(禅の無念無想、仏教の究極の境地とされる滅(めつ)受(じゅ)想(そう)定(じょう)〈滅尽(めつじん)定(じょう)、想(そう)受(じゅ)滅(めつ)定(じょう)ともいう〉)もある。
なお、宗教の瞑想は、その宗教の思想と密接不可分で、その一部であるが、近年では、瞑想技法の部分だけを切り離して、世俗的な目的に転用する場合があり、そうした場合は、本来の目的を実現しない場合もある。
3.学者による瞑想の定義や効用
精神科医の安藤治は、アメリカを中心とする西洋の瞑想(meditation)研究を紹介する『瞑想の精神医学』で、「伝統的により高度な意識状態あるいはより高度な健康とされる状態を引き出すため、精神的プロセスを整えることを目的とする注意の意識的訓練のことであるが、現代においてはリラクセーションを目的としたり、ある種の心理的治療を目的として行われることもある」と定義している。
ただし、瞑想が「より高度な意識状態あるいはより高度な健康とされる状態を引き出す」という主張は、現在主流の世界観・科学的な世界観をはみ出す(下に見て否定する)場合もあるので、瞑想状態を「変性意識状態」として位置付ける見方もある(この場合、やや否定的なニュアンスがある場合もある)。
上智大学グリーフケア研究所の葛西賢太は、瞑想を「日常生活の諸問題の整理や見直し、再活性化を意図して、日常の時間の中に、一定の時間を区切って、通常とは違う意識状態に自覚的に切り替えること、また、その方法」と定義している。同氏は、通常意識状態と変性意識状態の往来を「意識変容」と呼び、「意識変容を自覚しているマインドフルな状態」を、瞑想の基本的な状態(瞑想的意識状態)であると考え、この定義に当てはまるすべての行為を広い意味で瞑想ととらえることを提案している。
瞑想の具体的な効用として、感情の制御、集中力の向上、気分の改善等の日常的な事柄から、瞑想以外では到達不可能な深い自己洞察や対象認知、智慧の発現、さらには悟り・解脱の完成まで広く知られる。瞑想による特異な体験として、「変化しやすい強烈な感情、深いリラクセーションと高度の覚醒、知覚の明晰さの高まり、心理的プロセス(中略)への感受性の向上、身体を含めた対象物の知覚に関する変化や流動性の増加(対象恒常性の減少)、精神的コントロールの困難さに対する自覚、特に集中力を失わず、空想に陥らないようにすることの難しさの自覚、時間の感覚の変化、変性意識、他者との一体化の体験、防御心の減少、体験への開放性」などがあるとされる。
宗教哲学者の鎌田東二は、狩猟・漁猟を行っていた人々が、その技術を向上させるために修練し、それが武術や武道、スポーツとなり、また宗教的な行や瞑想になっていったと考える。生きるためには、食べる必要があり、人は生きるために命を殺害するが、人にとって命を食べることは、命がけの宗教的・呪術的行為であったという。狩猟は命の交換の行為であり、狩猟民は、命がけで動物たちとの戦いに挑み、その中で自然への畏怖の気持ちを高め、同時に恐ろしい動物を前にしても立ち向かうことができるよう、自己をコントロールし、動物と戦うために自己と戦わなければならなかった。鎌田東二は、このような心のコントロール・制御の方法を開発する道程から、夢見法や瞑想、観想が生まれ、さらにそのような集中や制御が、止観や禅を生み、山を歩き走ることが、山岳跋渉(ばっしょう)や修験道を生んだと考える。
4.近代の瞑想の歴史とセラピーとしての活用
あるがままを観察し、受け入れるという東洋の思想は、1960年代にアメリカのヒッピーたちが注目し、彼らは、精神的な成長を求め、東洋の伝統的宗教の瞑想を学んだ。例えば、ヒンドゥー教由来でインド人導師マハリシ・マヘーシュ・ヨーギーが広めた超越瞑想や、日本の禅仏教を学んだ。
20世紀のアメリカでは、裕福な階級は精神療法(サイコ・セラピー)を、精神病の治療だけでなく精神の健康にも活用していたが、1960年代後半に起こったヒューマンポテンシャル運動では、ゲシュタルト心理学などの人間性心理学と精神療法が結びついて一般に広まり、自己実現や自己成長の手段として重視された。
この運動の代表的な人物である禅の研究者アラン・ワッツは、東洋の宗教における修行と西洋の精神療法とを同様のものと考えて、瞑想が精神療法の文脈の中に取り入れられた。このことが、今日の一般での瞑想の実践や研究に大きな影響を与えていると考えられている。すなわち、西洋で瞑想は実利的な健康法、セラピーとして広く活用されているのである。
1970年代には、科学者を志す若者たちが、東南アジアやインドで瞑想の修行をするようになり、アメリカに戻って瞑想研究や普及活動をした。一方、インド人のヨーガの導師であるバグワン・シュリ・ラジニーシは、同時代にアメリカで活動し、現代人向けに多くの瞑想法を開発したが、瞑想の最終的な目的は、絶えず観照者にとどまること(ヨーガが説く真(しん)我(が)〈純粋(じゅんすい)観(かん)照者(しょうしゃ)〉)であると語ったという。
1980年代になると、徐々に科学的研究が発表され、瞑想する環境も整い、瞑想は広まっていった。安藤治は、瞑想はセラピーと言われることもあるが、精神的な病の治療を目指す精神療法ではなく、自己超越を促進する方法のひとつであると述べている。また、瞑想による血圧降下作用などの特殊な生理学的な効果が注目され、自己コントロールやリラクセーション法として研究されるようになった。
ここで、治療する病気や患者を適切に選べば、瞑想は、通常の医療を補完する補助的なものとして有用であるという見解があるが、その一方で、精神療法が大衆化し、瞑想がセラピーの場に取り入れられたために、瞑想は、従来の意味より大雑把に使われるようになって、十分適切な医学的な知識の下でコントロールすることは難しくなった面がある。
また、ヒューマンポテンシャル運動を引き継いだニューエイジでは、人間の脳の無限の可能性や、脳と宇宙エネルギーとの関係が(必ずしも科学的な証明がなく)信じられ、ヨーガ、レイキ、太極拳、自己啓発セミナー、禅、合気道、超越瞑想などが、霊的な成長をサポートするセラピーとして行われた。その中で、超能力を覚醒させることができると称して、シルバメソッド等、自己啓発セミナーでも瞑想が利用されているが、そうした瞑想の効能の主張は、さまざまな問題も指摘されている。
5.マインドフルネス瞑想の広がり
アメリカでは、医学者のジョン・カバット・ジンが、仏教の悟りの思想から、今この瞬間の対象に、良し悪し(好き嫌い)の判断をせずに、客観的に、意図して注意を向けるという「マインドフルネス瞑想」を医療化した。それは、慢性疼痛(とうつう)の(癌などの)患者の治療に活用したが、その後、その適応範囲は、うつ病、不安症、摂食障害、不眠症などの精神疾患まで広がっていった(マインドフルネス認知療法)。
こうして、瞑想からその宗教的な側面を整理してそぎ落とし、瞑想の科学的な研究が進み、2000年以降には、脳科学者の瞑想研究も増加した。そして、瞑想熟練者でなくとも、マインドフルネス瞑想のトレーニングで、脳の活動が変化するという科学的知見が示されて大きな衝撃を与えた。
その結果、マインドフルネス瞑想は今日に至るまで広まっていき、教育や福祉、職場のメンタルヘルスの向上のためにも用いられるようになった。アメリカでは2010年以降、ビジネスパーソン向けのマインドフルネスのワークショップが企業内外で開催され、Google や Facebook で導入されたことでも注目を集めた。感情のコントロールや職場の満足感の向上への効果が示され、2014年には『TIME』誌で特集も組まれた。
マインドフルネスは、それが由来する仏教の思想である「念」(サンスクリット語での「サティ」)の英訳であるが、この世俗化されたマインドフルネスは、仏教本来のマインドフルネスの思想と実践全体から切り離して、調整されたものであるため、それがもたらすいろいろな問題を指摘する人もいる。
6.心理学・心理療法に活用される仏教思想
なお、欧米の心理学・心理療法が仏教の思想を活用した近年の事例は、マインドフルネス以外にもある。例えば、アメリカの自己心理学者クリスティン・ネフは、社会的な競争に勝つことで自尊感情を高めることが幸福につながるという考えに疑問を呈し、仏教の思想に基づいて、セルフ・コンパッション(自分への慈悲、思いやり、優しさ)の研究を行って、(他との競争の勝利による)自尊感情が高くなくても、セルフ・コンパッションが高い人は、自分を受け入れ、幸福を感じ、不安や抑うつが低いという研究結果を示している。
ネフは、セルフ・コンパッションを、マインドフルネスを包含し相補する概念として提示しており、ジョン・カバット・ジンやマインドフルネス認知療法の創始者マーク・ウィリアムズも、「マインドフルネスはコンパッション(慈悲)を含んでいる」と主張している。
とはいえ、実際にマインドフルネス瞑想が活用される場合に、それがコンパッション(慈悲)を含むかというと、仏教本来の思想・文脈から切り離されて世俗的で実用的な目的に使われるためもあって、例えば、アメリカでは、軍事訓練にマインドフルネスを用いて、動じない兵士を作る試みなどがあって、瞑想が軍事利用されている事実もあるという。