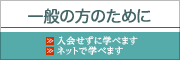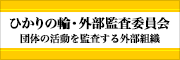2017年GW特別教本『苦しみを滅する仏陀の思想と瞑想』第1章公開
(2017年9月 4日)
1.はじめに
釈迦牟尼が説いた教えの目的は、苦しみを滅することである。その中核は、釈迦牟尼の初めての説法(初転(しょてん)法輪(ぼうりん))で説かれた中道・四(し)諦(たい)・八(はっ)正(しょう)道(どう)で明らかにされている。ここでは、まずそれについて詳しく検討する。
2.中道
釈迦牟尼は、快楽主義(左道)でもなく、苦行主義(右道)でもなく、中道を説いたことで知られる。
王子時代は、おそらくは欲楽にふけった生活を送ったと思われるが、人生の無常を感じて出家して修行に入ると、断食を含めた長年の厳しい苦行を行った。しかし、その末に、それで悟りを得ることができないとして苦行を捨て、「中道」に基づく修行に励んで悟り、目覚めた人(=仏陀)となったという。
その後、釈迦牟尼は、鹿(ろく)野(や)苑(おん)において、五人の比丘(出家者)に初めての説法を行ったが(初転法輪)、四諦・八正道よりも先に、この中道の教えを、以下のように説いたという。
「比丘たちよ、出家した者はこの2つの極端に近づいてはならない。第1に様々な対象に向かって愛欲快楽を求めること。これは低劣で卑しく世俗的な業であり、尊い道を求める者のすることではない。第2に自らの肉体的消耗を追い求めること。これは苦しく、尊い道を求める真の目的にかなわない。
比丘たちよ、私はそれら両極端を避けた中道をはっきりと悟った。これは人の眼を開き、理解を生じさせ、心の静けさ、優れた智慧、正しい悟り、涅槃(ねはん)のために役立つものである。」(パーリ語経典相応部から『世界の名著 1』中央公論社 p435-439)
なお、中道の教えと呼ばれるものには、いろいろな種類があり、初転法輪で説かれた中道は、快楽主義にも苦行主義にも偏らないという意味で「苦楽中道」ともいわれる。
3.四諦
「四諦」とは、四(し)聖(しょう)諦(たい)ともいわれ、4つの聖なる真理という意味がある。その4つの諦とは以下のとおりであり、まとめて「苦(く)集(じゅう)滅(めつ)道(どう)」と略称される。
1.苦(く)諦(たい)--この世は苦であるという真理
2.集諦(じったい)--苦の原因に関する真理
3.滅諦(めったい)--苦の止滅に関する真理
4.道諦(どうたい)--苦の止滅の道に関する真理
四諦は、釈迦牟尼が最初に説いた教えであり、仏陀の根本教説である。これは、人間の苦を滅するために説いた教えである。
この教えの要点は、この世・人生は一切苦であるが、苦の原因は煩悩であり、煩悩を滅すれば、苦は滅することができ、その具体的な道(八正道)があるというものである。この道を一言でいえば、この世、特に自己に対する執着(自我執着)を捨てることで、苦しみを滅すること(悟ること)ができるというものである。
なお、煩悩が苦の原因であるという教えは、「縁(えん)起(ぎ)の法」ともいわれる。ただし、縁起の法は、釈迦牟尼の死後、その意味が拡大され・複雑化したので、煩悩が苦の原因であるという最初期の縁起の法は、特に此(し)縁(えん)性(しょう)縁起という。よって、此縁性縁起を言い換えたものが、四諦の(集諦の)教えということもできる。
4.苦諦:この世は苦である--仏教の説く「苦」の意味とは
これは、この世界の一切が苦であるという意味だが、ここでは「苦」という意味を正確に知る必要がある。この漢訳語の苦の原語は、サンスクリット語ではドゥッカ(duhkha)といい、その原義は「不安定な、困難な、望ましくない」といったほどの意味である。
それから転じて、ドゥッカ(duhkha)には、二つの意味がある。
一つ目の意味は、日本語の苦と同じような意味であり、苦と楽のうちの苦のことである。より正確にいえば、この世界には、苦と、楽と、苦でも楽でもない(不苦不楽)の三つがあるが、その中の苦である。これは、苦と楽と不苦不楽を、異なるものとして区別し、苦は、楽と不苦不楽の対極にあるものという意味がある。
しかし、苦諦が説く苦とは、この意味でのドゥッカ(duhkha)ではないことが肝心である。これが理解できないと、仏教の教えが、不合理なまでにこの世界が苦しみだと強調していると誤解することになる。
二つ目の意味のドゥッカ(duhkha)とは、楽も不苦不楽も、それにとらわれると、それが変化して壊れるがゆえに苦しみの原因となると考える場合の苦である。苦と楽と不苦不楽を、別のものとはしない特殊な見方であり、苦楽は表裏一体という仏教の重要な思想が反映されている。
このドゥッカ(duhkha)の意味をよく表すものとして、仏教には「三苦」という教えがある。三苦とは、苦(く)苦(く)・壊(え)苦(く)・行(ぎょう)苦(く)である。
「苦苦」とは、苦しみそのものである苦である。すなわち、身体的・精神的な苦痛である。
「壊苦」とは、楽が変化して壊れる・滅する時の苦しみである。ここでは、仏教の中核の思想である無常が関係してくる。言い変えれば、今、楽であるものの先には、それにとらわれると苦しみがあることを意味している。これを苦楽表裏ともいう。
次の「行苦」も、無常に関係している。行とは、サンスクリット語でサンスカーラ(saṃskāra)であり、作られたものといった意味があるが、わかりやすくいえば、一切の存在である。
そして、仏教では、後に詳しく述べるが、あらゆる存在は無常であるから、一(いっ)切(さい)行(ぎょう)苦(く)といって、一切の存在は(とらわれれば)苦しみ(の原因となるもの)であると説く。こうして、行苦とは、(とらわれれば、無常であるがゆえに)一切の存在は、苦(の原因となるもの)であるという意味での苦である。
こうして、苦諦が説く「この世は苦である」ないしは「一切は苦である」という教えは、一切のものが、今この時点で苦痛であるという意味ではない。一切のものが、無常であることなどを背景として、とらわれれば、人にとって苦の原因となるという意味である。
ここでドゥッカ(duhkha)の原義に、先に述べたように、不安定な、望ましくないといった意味があることを思い出してほしい。これを踏まえると、仏教が説く「苦」=ドゥッカ(duhkha)とは、「不安定であるがゆえに、とらわれることは望ましくない(もの)」という意味だと解釈するとよいと思う。こうして、物事にとらわれない、執着しないというのは、仏教の思想の中核である。
5.四苦八苦
さて、三苦に加えて理解しておきたいのが、四(し)苦(く)八(はっ)苦(く)の教えである。日常用語の四苦八苦とは、非常な苦しみを意味するが、仏教用語では、人間の人生の様々な苦しみを分類して説いたものであり、人生は苦しみであると説くものである。ただし、この場合の苦しみも、先ほどの仏教的な広い意味での苦しみ(ドゥッカ〈duhkha〉)であることに注意されたい。
まず、「四苦」とは、①生・②老・③病・④死である。老・病・死はわかりやすいが、仏教では、生も苦しみとする。実際、妊娠・出産の過程は、いろいろな意味で思い通りにならず、母胎と胎児に、死を含んだ危険が伴う。
さらに、次の四つの苦を加えて「八苦」という。それは、⑤求(ぐ)不(ふ)得(とく)苦(く)--求めても得られない苦しみ、⑥愛(あい)別(べつ)離(り)苦(く)--愛する対象と別れる苦しみ、⑦怨(おん)憎(ぞう)会(え)苦(く)--憎む対象に出会う苦しみ、⑧五(ご)蘊(うん)盛(じょう)苦(く)である。
最後の「五蘊」とは、人または世界を構成するものを五つに分類したものである、具体的には、色(しき)・受(じゅ)・想(そう)・行(ぎょう)・識(しき)であり、その意味は、色が身体、受が感受作用、想が表象作用(イメージ)、行が意志作用、識が識別作用である。ここでは、色=身体のみが物質的な要素で、受・想・行・識は精神的な要素である。なお、広い意味では、世界全体を構成する物質と精神的な要素を意味する。
そして、五蘊盛苦とは、五(ご)取(しゅ)蘊(うん)苦(く)ともいわれ、その意味は、五蘊は全て無常であることなどから、とらわれると苦しみであるという意味である。すなわち、一切行苦とほぼ同じ意味だと解釈してよいと思う。
さて、ひかりの輪では、四苦八苦の教えをよりわかりやすくするために、後半の四つの苦しみに関して、⑤求めても得られない苦しみ、⑥得て執着したものを失う苦しみ、⑦(求めるがゆえに)奪い合うことによる苦しみ、⑧それがゆえに一切のものはとらわれれば苦しみになる、などと表現している。
これは、一切のものは、とらわれ求める限りは、その結果として、いろいろな苦しみが必ず生じることを強調したものである。
6.集諦:苦しみの原因は煩悩である--苦の原因とは何か
集諦とは、苦(く)集(じゅう)諦(たい)ともいうが、苦の原因に関する真理という意味であり、釈迦牟尼は「苦の原因は煩悩である」と説いた。この「集」の原語には、起源・原因・招集という意味がある。そのため、苦の原因ないし苦を招き集めるものは煩悩であるという意味で、集諦と訳されたと思われる。
なお、これは、先ほど述べたように、最も根本的な最初期の縁起の法である此縁性縁起と同一である。よって、集諦を中核とした四諦の教えを端的に表現したのが、此縁性縁起だという解釈もある。
では、次に、この「煩悩」とは何かというと、仏教が説く根本的な煩悩は、三毒といわれ、それは、貪(とん)・瞋(じん)・癡(ち)、すなわち貪り・怒り・無智である。ただし、ここの四諦の文脈における煩悩は、特に渇愛(渇いたように欲望を求めてやまない感情)のことを意味するという解釈もある。
そして、根本的な煩悩が苦しみを招く過程を示したのが、釈迦牟尼が説いた「十二縁起」という教えであるとされるので、多少難解ではあるがここで解説したい。なお、この十二縁起の教えの中では、渇愛は「愛」と漢訳されたものである。
7.十二縁起:無智から苦しみが生じるプロセス
「十二縁起」とは、人間の苦しみの原因(=煩悩)を、順に分析したものであり、それが「無明」から始まり「老死」で終わる十二の因果関係の連続で表現されるので、十二縁起と呼ばれる(縁起とは因果関係という意味がある)。十二因縁、十二支縁起、十二支因縁などと訳される場合もある。
その十二の因果関係の連続とは、以下のとおりであるが、これは、「無明」によって「行」が生じ、「行」によって「識」が生じ、最後に、「生」によって「老死」が生じるという意味であると理解されたい。
1.無明(むみょう) - 煩悩の根本。根本的な無智。真理がわからないこと。
2.行(ぎょう) - 意志作用・志向作用。
3.識(しき) - 識別作用(物事の区別・差別・好き嫌いの精神的作用)。
4.名(みょう)色(しき) - 人の心身。名が精神現象(心)、色が物質現象(肉体)を意味する。
5.六(ろく)処(しょ) - 五感と意識。六処とは、六つの感覚器官といったほどの意味で、六つとは五感と意識のこと。
6.触(そく) - 六つの感覚器官が、それぞれの感受対象に触れること。外界との接触など。
7.受(じゅ) - 感受作用。六処で外界などに触れた結果として感じること、感覚。
8.愛(あい) - 渇愛・愛着。
9.取(しゅ) - 執着・とらわれ。
10.有(う) - 存在・生存。
11.生(しょう) - 生まれること・出産。
12.老(ろう)死(し) - 老いと死。
8.十二縁起の法の解釈:様々な解釈があり多少難解
十二縁起の法の解釈は、率直にいえば、様々な解釈があって、多少なりとも難解である。全体を見れば、最後の方に、生=生まれることがあるから、少なくとも前半は、生まれる前のプロセス=胎児の胎内でのプロセスだと解釈して、胎生学的な解釈をすることが少なくない。
また、釈迦牟尼の死後は、十二縁起が、前世と現世(今生)と来世の三つの生にまたがった過程をあらわしているとする解釈(三(さん)世(ぜ)両(りょう)重(じゅう)の縁起)も現れた。そこで、こうした解釈のばらつきを越えて、十二縁起のエッセンスと思われることをまとめておきたい。
第一のエッセンスは、すべては「無明」から始まるとしていることである。この無明とは、元の意味は、目が見えないという意味で、転じて聡明さに欠けるという意味を持つ。そして、仏教用語としては、人生や事物の真相・実相に明らかでないこと=無知であることを意味する。
より具体的には、すべては無常であり固定的なものは何もないという事実に、無知なことであるとされる。これを仏教用語で言い換えると、縁起・無常・空といった真理を知らないことなどと表現される場合もある。この縁起・無常・空に関しては、第二章で詳しく説明する。
そして、釈迦牟尼は「無明こそ最大の穢れである。比丘(出家者)たちよ、この汚れを捨てて、汚れなき者となれ」と説いたという(法句経243)。また、仏教用語の中で、この無明と同一とされるのが、痴(愚痴)であるが、この痴も、煩悩の中でも最も基本的なものとされる。三つの根本煩悩(三毒)とか、六つの根本煩悩とされるものの一つであって、その中でも最も根本的なものとされる。
こうして、無明とは、人の持つ根本的な無知であって、すべての煩悩の根源とされるものである。その意味を込めて、以下では、根本的な「無知」ではなく、根本的な「無智」という表現を使うこととする。では、次に、より詳しく無明の意味を理解することにしよう。
9.四(し)顛(てん)倒(どう)
この根本的な無智に関連して、釈迦が悟った直後に、まず説いた教えと思われるのが、四顛倒である。顛倒の原義は、ひっくり返ることであるが、それから転じて、真理とは逆さまな見方=間違った見方といったほどの意味になる。
具体的には、釈迦牟尼は、人は、
1.無常なものを常(恒常的なもの)であると錯覚している。
2.無我を我と錯覚している。
3.苦しみであるものを楽であると錯覚している。
4.不浄なものを浄であると錯覚している。
と説いた。
ここで、無我とは、私・私のもの・私の本質ではない、という意味である。よって、無我を我と錯覚しているということは、私・私のもの・私の本質ではないものを、私・私のもの・私の本質と錯覚しているということである。
なお、我は、永久不変の本質という意味があり、そのため、無我は、永久不変の本質がなく、固定した実体がないとも解釈される。これは、大乗仏教が説く空の思想と繋がるものである。
この中の無常・無我・苦の三つは、頻繁に説かれる仏教の重要な教えであり、仏教の基本的な現実認識である。詳しくは第二章に述べるが、ここで簡潔にいえば、「この世の一切のものは、無常であり、変化して消えていくものであって、私自身も、必ず老い病み死ぬものであるから、本当の意味で、私とか、私のものといえるものは全くなく、一切は(とらわれるならば)苦しみである」ということである。
にもかかわらず、実際には、悟っていない人は、無常であることを理解せず、本当の意味で私・私のものなどはないことを理解せず、そのために(とらわれるならば)苦しみ(の原因となるもの)を楽だと錯覚して、それにとらわれるという間違いに陥っているというのである。
10.四顛倒と十二縁起
この四顛倒の教えを踏まえて、十二縁起のプロセスを考えてみよう。無常を常、無我を我、苦を楽、不浄を浄と錯覚すると、実際はとらわれれば苦しみ(の原因)となるものを、楽と錯覚することになる。
すると、この無明=無智のために、無明の次の「行」(意志作用)が生じる。すなわち、何らかの意思・欲求が生じるのである。その後に「これが良い悪い」といった「識」(識別作用)が生じる。そして、その後に、母体内の胎児の意識は、育ちつつある自分の「名色」(=自分の心身)に執着するようになる。
そして、「六処」(感覚器官)によって外界に接触して(「触」)、色々なものを感じるようになり(「受」=感受作用)、その結果、いろいろなものを愛着して求めるようになり(「愛」=渇愛)、いろいろなものにとらわれ(「取」)、自分の存在(「有」)にとらわれて生まれる(「生」)が、その結果、老いと死という苦しみに至る。このように理解することができる。
そして、このプロセスをどこかで切断・捨断できれば、苦しみが生じないということになる。
11.仏教心理学的な無智の説明
次に、仏教が育んだ仏教の心理学の視点から、無智を根源とする煩悩の形成について述べる。仏教には、唯識思想をはじめとして、人の心を分析した心理学というべきものがある。その中には、根本的な無智からどのように煩悩が生起していくかの過程も分析されている。
まず、(悟っていない人の)根本的な無智として、「(自分の)覚醒状態を見失っているという無智」があるという見解がある。覚醒状態とは、仏教では涅槃であり、仏陀の覚醒状態である。
そして、この根本無智と同時に生じるのが、「自己と他者を区別する無智」であると説く。これを言い変えれば、覚醒状態では、自己と他者を区別しないが、それを失うと同時に、自己と他者を区別する意識が生じるということである。すなわち、仏教では、この世界の真実は、自己と他者は繋がっていて別ものではないが、それを人は理解せずに、自己と他者を区別する錯覚に陥っていると説くのである。
そして、自己と他者を区別すると、自分・私という意識が生じ、他者よりも自分に執着する。これを自我執着、我執、我見、我愛などという。
そして、外界に、自分に心地よいものと不快なものがあると感じるようになる。快不快、好き嫌いの区別が生じる。そして、心地よいものを、自分のものとしよう、自分のものとして増やそうという「貪り」、その逆に、不快なものを排除しようとする「怒り」が生じる。
これが、無智から、貪り、怒りが生じるプロセスであり、これら三つを三毒(三つの根本煩悩)ともいう。この三つの煩悩が、他の様々な煩悩(下位の煩悩)をもたらす。妬み・慢心・愛着などの様々な煩悩が生じる。
しかし、この煩悩は苦しみをもたらす。四苦八苦の教えで解説したように、貪り求めても、得られない苦しみ、得たものさえ失う苦しみ、そして、求めるがゆえに奪い合う苦しみが生じる。こうして、無智から様々な煩悩が生じて、様々な苦しみが生じる。
最後に参考までに、大乗仏教の唯識思想では、痴(根源の無智=自他の区別)が、我痴(自我意識)を生じさせ、それが我愛(自我執着)を生じさせ、我慢(慢心・私は偉い・優れているという意識)を生じさせると説いている。ここでは、自我執着の中で、慢心(我慢)が強調されている。
12.滅諦と道諦
四諦の第三である「滅諦」は、苦(く)滅(めっ)諦(たい)ともいう。苦の止滅に関する真理という意味であり、「苦は滅する」という教えである。
より具体的には、苦しみの原因は煩悩であるから、煩悩を滅するならば、苦しみは滅することができるということである。
そして、四諦の第四の道諦は、苦(く)滅(めつ)道(どう)諦(たい)ともいう。苦を止滅する道に関する真理という意味である。
そして、苦の原因は煩悩であり、その根源は無智であるから、苦を止滅する道とは、無智を滅して、煩悩を滅して、苦しみを滅する道である。
これが、まさに仏道修行のことであり、釈迦牟尼の直説の教えでは、この修行体系をまとめて、「七(しち)科(か)三(さん)十(じゅう)七(しち)道(どう)品(ぼん)」という。
ただし、その中で、釈迦牟尼の初めての説法で四諦とともに説かれ、初期仏教において最も主要な修行体系が、「八正道」である。この八正道について、第二章で詳しく述べることにする。
なお、八正道以外の七科三十七道品の修行体系に関しては、本教本の主旨を外れるので、『2016~17年 年末年始セミナー特別教本「四無量心と六つの完成」』を参照されたい。