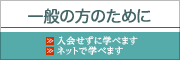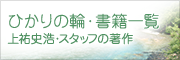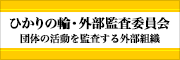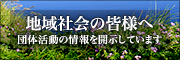2021年夏期セミナー特別教本「知足と感謝の瞑想 感情と健康の科学 縄文の精神性と進化心理学」
(2025年4月24日)
2021年夏期セミナー特別教本「知足と感謝の瞑想 感情と健康の科学 縄文の精神性と進化心理学」
第1章 仏教的な幸福の哲学:知足・感謝・慈悲
1.二つの対極的な幸福観
現代の人々、特に先進国の人々は、ほとんどの人が、昔の人や途上国の人に比べるならば、飢えることもなく健やかに生きることができる。
しかし、資本主義競争社会の中で、健やかに生きるだけでは「足るを知る」ことは乏しく、自と他の優劣を絶えず比較して、「今よりもっと」、「他人よりもっと」と、際限なくさまざまなものを求めて、自己の優越感や勝利を喜び、劣等感や敗北を嫌うという傾向が、全体に広がっていると思う。それが幸福への唯一の道であると、さまざまな形で子供の頃から教育されて、1つの信念・信仰のように浸透しているのではないだろうか。
しかし、現在は、それがあまりに行き過ぎてしまって、逆に、いろいろな意味で不幸になっている人が多いのではないかと思う。日常のさまざまな精神的なストレス・緊張・不安・うつ、それと連動する不健康・病気、人間関係の問題・破綻が生じている。数万人の自殺者、数万人の孤独死、その10倍といわれる未遂による緊急搬送、500万人と推計されるうつ病などは、その一環の現象ではないだろうか。
2.勝利至上主義の競争の弊害
競争が必要だという考え方に反対ではない。しかし、競争の本来の目的、というか、その理想のあり方は、全体のレベルを向上させるための切磋琢磨であって、言い換えれば、競争相手への尊重と愛に基づいたものだと思う。それは、ゲームの勝ち負けのように、真剣にであっても、楽しむべきものだろう。
しかし、自己の勝利のみが唯一の目的・善となり、敗北は無価値で悪となれば、それは、人を幸福にするより、不幸にすることが多くなるのではないだろうか。勝利至上主義となれば、勝利のための不正手段も横行し、それは真の切磋琢磨・全体の向上を阻む。特定企業が独り勝ちして市場を独占すれば、健全な競争は妨げられ、全体の向上を阻む。
また、敗北への不安・恐怖・嫌悪が強くなりすぎると、精神的な苦悩・ストレス・うつ状態が強くなり、心身を病み、競争に参加せずに、人間関係が保てず、引きこもる人々も増える。すると、これも健全な競争や全体の向上・幸福を阻む。さらに、勝者への妬みと敗者・劣者を蔑む心理が広がり、他者への尊重や愛を阻むことになる。
個々人の日常行動や企業の活動に限らず、今、行われている東京五輪を見ても、SNSにおいて、敗者に対する蔑みや、勝者に対するやっかみなどによる誹謗中傷が大きな問題となった。また、スター選手のメンタルヘルスの問題が、これまで以上に大きな注目を集めた。ロシアの選手は、ドーピング問題のために、国の代表として参加を阻まれた。
3.東京五輪と新型コロナ問題
さらに、五輪競技とともに、新型コロナ感染の急激な再拡大という重大な健康問題が、同時進行している。普段であれば、スポーツ競技は、戦争とは違って平和の象徴であり、五輪は平和の祭典であるが、新型コロナの感染が広がる今度ばかりは、経済活動にしてもスポーツにしても、競争の勝利による幸福の追求と、健やかに生きるという幸福が、必ずしも両立せずに、明らかに矛盾するという状態が起こっている。
選手団の行動範囲を、選手村・試合会場・練習会場に制限し、五輪選手団と一般人との間の感染が起きないように努めているために、五輪と感染拡大に直接的な因果関係はなく、感染力の高いデルタ株が原因との見方もあるが、五輪の開催で、「コロナ問題は大したことない」「五輪だってやっている」と考えた国民の気が緩んで、人出や飲酒が増え、感染拡大につながったという見方は少なくない。
本来は、健康を考えるならば、感染しかねない安易な行動は控えて、慎重な行動を続けるべきだろうが、資本主義競争社会の中で培われた欲求と行動パターンや、それによって蓄積される日常のストレスなどのために、ある段階で我慢ができなくなったり、何かをきっかけに油断して、賢明な行動ができなくなったりする面もあるのではないか。
そして、結果として、今回の東京五輪は、これまでの五輪よりもはるかに印象に残るものとなるだろうし、いや単に印象に残るというのではなく、新型コロナ感染の急拡大とセットになった東京五輪の開催は、今後の日本社会、五輪、世界の価値観にも、大きな影響を与えるような出来事の一つになる可能性があるのではないか。
4.現代人は際限ない欲求の虜(とりこ):今よりもっと、他人よりもっと
現代人に限らないが、普通の人は、幸福とは、「今ないものを、未来に得て感じるものだ」とばかり思う傾向がある。すでに得ているものには、あまり幸福や感謝は感じないのである。そして「今よりもっと」と求めて、幸福を得ようとする。この変形としては、「今より良かった昔を未来に回復してこそ、幸福になれる」と思ったりする場合もある。
これは、いずれも、現状に幸福や感謝を見出すのではなく、現状にないものを未来に得てこそ幸福になるという考え方だ。その背景には、絶えず現状の自分や、他人の自分に対する扱い(を含めた取り巻く環境)に対する不満・嫌悪・怒りがある。
また、その中で、前にも述べたが、自分と近しい友人・知人と自分を比較して、より恵まれている時に幸福を感じる傾向がある。すなわち、優越感を求めて喜び、劣等感を嫌がり苦しむ。そして、「他人よりもっと」と求めて、幸福を得ようとする。
このことをある心理学者は、現代人の幸福の基準は、自己愛の充足の有無だと言う。自と他を比較して、優越感を感じられる自己を愛し、劣等感を感じる自己は愛せない(自己嫌悪・コンプレックス)ということだろう。
「今よりもっと」と求めることも、「他人よりもっと」と求めることも、現状の自分や他人に不満があり、幸福・不幸が比較の問題になっている点については変わりがない。今後得るものが、今得ているものと比較して勝っていれば喜びになり、近しい友人・知人と比較して勝っていれば喜びになる。しかし、こうした幸福の追求は、際限のない欲求と、それによるさまざまな苦しみの原因となる。
5.際限なく求める心理構造と、それを裏付ける脳科学的な事実
それは、なぜかというと、たとえ今ないものを求めて得たとしても、得ると間もなくそれに飽きてしまい、さらに求める心理が生じるからである。
そもそも、その幸福の本質は、今ないものを未来に得るという、今と未来の比較によって生じる幸福であるから、それを得てしまった後は、その新しい今の状態と比較して、さらに、より優れているものを未来に求めて得られなければ、幸福を感じなくなってしまう。得たものには飽きてしまい、より強い刺激でないと幸福を感じられないということである。
最近著しく発展してきた脳科学の知見によれば、これは、脳内神経伝達物質であるドーパミンと、その神経回路の特性であるといわれる。ドーパミンは、何かを得た時に喜びを感じさせる物質であり、それゆえに、何かを得ようとする意欲も形成するといわれている。
しかし、何度も同じものを得ているだけでは、ドーパミンは分泌されなくなり(喜びを感じなくなり)、ドーパミンが分泌されて喜びを感じるには、さらに強い刺激が必要となるのだという。
その意味では、覚せい剤による快感を持続させるために、摂取量をどんどん増やす必要があるといわれるように、すべての人間の欲望は、中毒症状や依存症といわれるものと似た一面がある。
覚せい剤のように、得られなくなった時に酷い禁断症状を起こしたり、ただちに著しい心身の不健康をもたらしたりすることはないにしても、喜びを感じ続けるためには、より多くのものを得続ける必要があり、それができないと苦しみになるということである。
この人間の苦しみのパターンを分類して説いたのが、「四苦八苦」という仏教の教えである。
6.仏教が説く四苦八苦の苦しみ
こうして際限なく欲求する中で、求めて得られるのではなく、得られない場合や、得たために執着しているものを失う場合は、自分と他人が互いに求めるがゆえに、奪い合いとなって、憎しみ合う苦しみなどが生じる。こうした人間に生じやすい苦しみのパターンを説いたものが、四苦八苦である。
それは、生(しょう)・老・病・死の四つの苦しみと、求(ぐ)不(ふ)得(とく)苦(く)(求めても得られない苦)、愛(あい)別(べつ)離(り)苦(く)(愛着する者と別れる苦)、怨憎(おんぞう)会苦(えく)(憎い相手と会う苦)、五(ご)蘊(うん)盛(じょう)苦(く)を合わせた合計八つの苦しみである。こうして際限なく求め、それを妨げる物事を嫌がる(怒る・憎む)ならば、人は、必然的に、さまざまなパターンの苦しみや不安や恐怖を感じることになる心理的な構造を持っていることがわかるだろう。
また、別の視点で見るならば、さまざまな心の苦しみに加えて、そのストレスによって、心身の健康を失い、病みやすくなり、人間関係が悪化し、知性も低下する。これは、ある心理学が説く、幸福になるための基本的な条件、心の安定、知性、健康、人間関係が損なわれることを意味する。
なお、心・感情と心身の健康の関係については、第2章で詳しく述べたいと思う。
7.知足と感謝:今あることに気づく幸福
一方、「今よりもっと」、「他人よりもっと」と求め、今ない幸福を未来に求めて得る(勝ち取る)幸福ではなくて、今すでに与えられている幸福に気づくことによる幸福がある。求める幸福(勝ち取る幸福)と、気づく幸福である。
得ても得ても、「もっともっと」と、際限なく幸福を求める性質があるとするならば、この「今ある幸福に気づく幸福」に気づかず、今ない幸福を未来に求め続けることによって、まるで回し車の中のリスのように、全く前に進むことなく、疲弊消耗するだけで、本当の意味で幸福になれず、充足することなく、一生を終えることになる。
言い換えれば、他者の視点から見れば、すでに十分に恵まれているにもかかわらず、本人はそう感じておらず、ひどく乾いており、現状の自分や他者に不満が強く、未来に期待とともに不安があり、過去には後悔や恨みを抱き続けるのである。
8.仏陀が説いた人間の得ている膨大な恵み
そこで、今すでに与えられている恵みに気づくためには、普段とは異なる大きな視点に立ってみることが役に立つ。その視点で説かれたものが、人間に生まれることの貴重さを説いた仏陀の教えである。仏陀は、無数の生き物の中から、人として生まれる可能性は非常に小さく、夜空の星の数と昼間に見えるか見えないかの星の数にたとえられると説いたという。
これを現代的に言い直してみるならば、無数の生き物の中から人間に生まれ、多くの人間の中から21世紀という人類史上、最も恵まれた時代に生まれ、その中から安全・豊か・長寿という三拍子が揃った日本人に生まれ、さらには精神的な幸福の智恵である仏法を学ぶことができているということは、「天文学的な奇跡である」と表現できるのではないか。
39億年前に生まれた地球上の生命は、まさに無数であり、足の下に百万匹の微生物がいるといわれる。20万年ほど前に誕生した現在の人類(現世人類・ホモサピエンス)は、その誕生以来、ある科学者のグループによれば、1千億人ほど生まれたと推計される。
その1千億人の現世人類の中から、高度な都市文明が発達した21世紀の現在に生き残っている者の数(すなわち現在の世界人口)は、約77億人弱だという(2019年時点での世界銀行の推計)。その中で日本人は、1億2300万人強とされる。この意味では、五輪に例えるならば、日本人は皆が金メダル集団であるといっても足りないほどに、奇跡的なまでに恵まれた境遇にあるということができると思う。
9.間違った幸福観から抜け出す思想を学ぶ尊さ
さらに、仏陀は、人間に生まれたとしても、多くの人間の中から、仏法に巡り合って、その精神的な幸福を得る縁(法縁)を得る可能性は非常に小さく、それも、また夜空の星の数と昼間に見えるか見えないかの星の数にたとえられると説いたという。こうして仏教では、法縁のある人間の転生を「宝のように貴重な人間転生」などということがある。
現代社会の人々は、先ほど述べたように、奇跡とさえいうべきほどに恵まれていながら、本人たちが自覚するところとしては、依然として非常に多くの人々が、さまざまな意味で苦しんでいる。
そして、その苦しみをもたらしている原因と、その解消の道を説く仏陀の教えや、それと同じ本質を持った心理学的・科学的な幸福の思想を学んでいる人たちが、この世界の中でどのくらいいるだろうか。
そうしたことは何も考えることがなく、心が絶えず際限のない欲求に巻き込まれて、求めても求めても本当の幸福・充足・平安にはたどり着かないうちに、あっという間の人生を終えてしまう人の方が、はるかに多いだろう。
なお、この点で誤解がないようにしておきたいが、私は、仏陀、すなわち仏教開祖の釈迦牟尼の説いた初期仏教の教えの趣旨は、科学的・合理的な裏付けがない、いわゆる信仰・神話・宗教の類のものではなく、心身の苦しみを解消する高度な心理学・実践哲学であると考えている。
実際に、私に限らず、インド思想の専門家の中にも、釈迦牟尼を「偉大な心理学者である」と評価する人もいる。そうした仏教の心理学的・科学的・合理的な幸福の思想を評価しているのであり、宗教としての仏教や、そのさまざまな宗派を特別視・絶対視してはいない。
10.足るを知る「知足の幸福」の思想
そして、自分たちが、この地球の生命圏と人類社会の中で、金メダル集団以上ともいうべき、奇跡的なまでに恵まれた境遇を得ている事実に気づいたならば、「このような自分たちが不幸であるならば、他の誰が幸福になることができるだろうか」という気づきが出てくるのではないか。
さらには、際限のない欲望のために、客観的に見れば奇跡的なまでに恵まれている自分たちが、幸福を感じていないとすれば、「自分が日頃羨んでいる人たちも、本人は自分が思っているように幸福ではないのではないか」ということにも気づくのではないだろうか。
言い換えるならば、際限のない欲望を乗り越えて、すでに得ている膨大な恵みに気づいて、いわゆる「足るを知る」ということがなければ、はた目には、どんなに恵まれていても、本人は幸福を感じていないのではないかということである。
11.自分が羨む存在も、必ずしも幸福ではない
それは、はた目には世界で一番恵まれているといわれる人たちにさえ当てはまる。世界最高の権力を持つとされる米国の大統領を例にとれば、私は、トランプ元大統領は、絶えずいろいろな人たちと闘い、怒り、精神は不安定で、普通の人よりも幸福そうには見えなかった。
大富豪といわれるロックフェラー氏の一人は、自分の財産を愛する人はいても、自分を本当に愛する人はおらず、死ぬときは孤独感の中で、「金には何の意味もなかった」と言って死んでいったという有名な話があるという。
現代の稀代の実業家にして富豪となった故スティーブ・ジョブズ氏(アップルの創業者)も、癌で若くして死ぬ間際には、(事業・ビジネスは)「向う(死後の世界?)には持っていけない」と言って、自分の人生の時間の使い方を悔やんでいたともいう。
最近よく話題になるのは、人類有数のアスリートたちや、皇室の人たちのメンタルヘルスの問題である。人類の中で最高のパフォーマンスを発揮する体を持ち、世界中の称賛を集める人たちでさえも、世界有数の社会的地位を有する特別な家族の人たちであっても、本人としては、必ずしも幸福ではなく、自分を取り巻く周辺環境に、心理的に適応できていない。そうした事例が、最近はますます目立つようになった。
そして、新型コロナのパンデミックが発生して以来、世界最強の軍事力と経済力を誇る米国が、世界最多の感染者・死亡者を出し、平均寿命が大きく減じるとともに、人種差別や大統領選にまつわる国内社会の分断が浮き彫りとなったことは周知の事実である。
12.幸福・不幸は心の現われ
こうしてみると、幸福や不幸とは、その人の心の持ち方・物の見方や視点によって生み出されるものではないだろうか。すでに与えられている幸福は膨大であるが、それを見なければ、幸福にはならない。
逆にいえば、上には上があるから、自分がまだ得ていないものばかりを見れば、それはいくらでもあって、その意味で、不幸・不遇は尽きることはない。
これを一言でいえば、「幸福を見る者は幸福になり、不幸を見る者は不幸になる」ということである。これに関連して、仏教では、「全ては心の現われ」という教えがある。これは、幸福・不幸も、心が作り出すものということである。
13.気付く幸福から生まれる感謝の心
広く大きな視点に立って、自分がすでに膨大な恵みに浴していることに気づくならば、そこから生まれてくる視点がある。
それは、自分の幸福が、多くの人々や生き物の労苦・犠牲のもとに成り立っており、しかも、その多くの人々や生き物の中には、自分よりもはるかに恵まれない境遇にある者たちが無数に存在しているということである。
少し考えても、毎日食べる物のために、多くの生き物が殺されている。味覚を喜ばせる美味しい食べ物も、その元になった殺された生き物の苦しみがある(ということを考えすぎると美味しくなくなるが)。そもそも、他の生き物を殺さずに生きることはできない体を人が持っていることは、仏教では「宿(しゅく)業(ごう)」(宿(しゅく)命(みょう)の業)ともいうことがある。
食べ物に限らず、世間で一般に幸福とされているものは、実際には、何かしら他の不幸の上に成り立っているものばかりである。お金持ちであるという喜びは、自分よりも貧しい他者がいてこそ生じるものだ。いつでもどこでも誰でもが、これ以上のお金を持っていれば金持ちであるという絶対的な基準はなく、自分に近しい人たちとの比較の問題である(途上国から見ると日本人は、皆が王侯貴族に見えるとも聞いたことがある)。
そして、財物に限らず、美しい容姿とか、美しい異性を得るとか、優れた学力・学歴・知性・体力・名誉・賞賛・地位・権力を得るといったことも、全ては、他との比較の問題であって、それを得られない多くの人たちがいるからこそ、得ることができる人がいるという奪い合いの構造にほかならない。普通の意味での幸福は、他者の不幸・苦しみの上に成り立っているのだ。
こうしてみると、偶然かもしれないが、「感謝」を「謝罪を感じる」と書くのは、理にかなっているのではないだろうか。そう書くようになった由来は知らないが、自分の幸福が、他の労苦の犠牲の上にあるのが事実であるのだから。
14.感謝に基づく恩返しとしての利他の行為
そして、感謝が深まるならば、それに基づいて「恩返し」としての利他の心が生じてくる。これは、仏教の教えに限らず、一般にも、自分の成長を支える労苦を背負った存在、例えば、親・親族・教師・先輩・同僚・出身地・社会的な自立や成功を助けてくれた人や集団・組織に対する「恩返し」などが、よくいわれる。
この感謝に基づく恩返しとは、労苦をかけた者に対して、今度は自分がその者の幸福のために労苦を厭わない、ないしは自分の幸福をその者と分かち合い、その者の苦しみを自分が分かち合うといったことだろう。これは一般的にも、仏教的にも、利他、利他心、利他の行為などといわれるものとなる。仏教では、慈悲の心と実践などともいう。
15.利他の心・行動は自分を利する:利他主義は賢明な利己主義
そして、感謝に基づく恩返しの利他の行為は、実際には、他人・他者ではなく、自分自身こそを利するものである。
この「利他=利己」という思想は、仏教開祖の釈迦牟尼も説いた仏教伝統の思想である。釈迦牟尼は、実子の出家僧ラーフラにも、慈悲の瞑想(正確には慈(じ)・悲(ひ)・喜(き)・捨(しゃ)という四(し)無(む)量(りょう)心(しん)と呼ばれる瞑想)によって、自分の怒り・冷酷さ・不満(貪り)の心などを浄化してなくすことができると説いている。
また、ヨーロッパ有数の知識人とされ尊敬を集めるジャック・アタリ氏も、今後の人類社会のために、「利他主義こそ最も賢明な利己主義」という考え方を提唱している。「善人は馬鹿を見る」「悪人が世にはばかる」のではなく、やはり真実は、利他を行う者は自らも幸福になり、自己中心的な者は自ら不幸になるということである。
実際に、際限のない欲望に陥らずに、足るを知り、感謝し、利他の行為を行う者は、まず、心が穏やかで充足して平安である。過剰な嫌悪・不安・恐怖・怒り・憎しみがなく、それは心身の健康・長寿をもたらす。さらに、心身の健康・安定は知性を高める(これは高齢期の知性の維持にも重要だ)。そして、人間関係を損なうことが少なく、逆に温めることができる。
こうして、前に述べた、心理学が説く、幸福のための基本的な4つの要素、心・健康・人間関係・知性が向上していく。これは、ことわざ・格言の世界でいえば、「笑う門には福来る」、「果報は寝て待て」といったことにも通じることだと思う。
16.万物への感謝と恩返し:仏教の菩薩道
さて、日常の常識・固定観念を乗り越えて、私たち個々の人間を支えている存在=恩人を科学的に考えると、突き詰めるならば、それは、宇宙・世界の万物ということになる。実際に、私たち人間は、自分たち一人では、幸福になるどころか、生きることさえ、生まれることさえできない。それは、俗に恩人といわれる人たちがいたとしても、まったく同じである。
そして、例えば、雄大な大自然に触れたりすると、謙虚な気持ちになり、自分たち人間という存在は、この世界で非常にちっぽけな存在であって、世界万物に絶えず、さまざまな形で支えられながら存在しているものだと感じることがある(雄大な大自然を前にした人に生じやすい、こうした心理的な気づきを、研究者は「AWE(オウ)体験」と呼んでいる)。
実際に、恩人とされる人間だけでなく、人類社会全体、すべての生き物を含んだ地球生命圏、さらには、地球の存在を可能ならしめる太陽系・銀河系といった広大無辺な宇宙のシステム全体に、我々の生命と幸福は支えられている。
そこで、仏教の教えの中には、すべての生き物・万物を恩人と見て感謝し、すべての生き物の恩に報いることとして、すべての生き物を利する実践をする道を歩むというものがある。これはいわゆる「菩薩」としての生き方、「菩薩道」である。菩薩は、すべての生き物を恩人と見て、恩に報いるために、その者たちすべての苦悩を取り除くために、仏陀の(悟りの)境地を求める(これを発(ほつ)菩(ぼ)提(だい)心(しん)という)。これをまとめれば、万物への感謝と恩返しの利他の実践である。
17.知足・感謝・利他と謙虚・他者の尊重
また、こう考えてみると、「足るを知る」「感謝する」「恩返し・利他の実践」といったものの背景には、さまざまな宗教・思想・倫理観などで重視される、いわゆる普遍的な美徳である「謙虚さ」「他者の尊重」があるのではないだろうか。そして、これと対極的な心の働きが、「際限ない欲求(貪り)」、「不満」、「自己中心・奪い合い」であり、その背景にある「傲慢」・「他者の蔑視・差別」といったものではないだろうか。