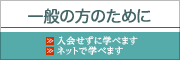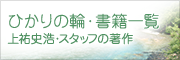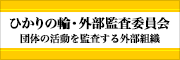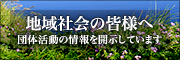2020年夏期セミナー特別教本「新型コロナ問題と免疫力の強化 文明周期説と循環の法則」
(2025年4月24日)
2020年夏期セミナー特別教本「新型コロナ問題と免疫力の強化 文明周期説と循環の法則」
第1章 感染症予防のためのヨーガ・仏教の修行の意義
1.はじめに:自然免疫の重要性
後からその理由を詳しく述べることにするが、新型コロナウイルスの感染症に対応する上で、一番重要なことの一つが、政府の政策やワクチン等の医療技術の開発ばかりに頼らず、個々人がその免疫力・抵抗力を強めておくことだと思う。政府の政策やワクチン等の医療技術では、どうにも追いつかない問題であるからだ。
その背景には、結論からいうならば、世界中で大変多くの方が亡くなった事実は大変痛ましいことであるものの、この問題の本質として、現代社会が、その生き方・活動の在り方から、自ら作り出した人災的な側面を持っているということがあると思う。
さて、これも後から詳しく述べるが、免疫力には、生まれつき備わっていて、どんなウイルスが体内に入って来ても即座に機能する「自然免疫」と、あるウイルスが入って来た後に暫くして後天的に獲得される「獲得免疫」の2つがある。よって、新型コロナウイルスを含めた未知の感染症に対しては、まずこの自然免疫を強めておくことが重要になる。
そして、この自然免疫を強めてくれるものが、私たちが普段から学習・実践しているヨーガ・仏教の思想・行法・瞑想などである。それらがどのように免疫力を高めるかという点について、なるべく詳しく紹介したいと思う。
2.ヨーガの体操や呼吸法の身体的な効果
感染症の予防において、低強度運動が、免疫力の向上に役立つといわれている。その中の一つが、ヨーガの体操(体位法・アーサナ)である。感染症の専門家も、ストレッチングヨーガの効果の研究結果を発表している(※参考文献1)。
運動と免疫力の関係で一つ注意すべきは、激しすぎる運動は、逆に免疫力を損なうことである。よってアスリートは、逆に免疫力が弱く感染症にかかりやすいという専門家の見解が少なくない(※参考文献2~4)。免疫力を消耗してしまうという感じらしい。
この低強度運動の効果には色々なものがある。後で述べるように、筋肉を弛緩させることによる精神的な効果もあるが、物理的・身体的な効果としては、血液循環の改善や体温の上昇などが挙げられる。
血液循環が良くなると、免疫細胞が体全体を巡ることができる。そして、一般に体温が上昇すると、免疫力が向上するといわれている。そして、この低強度運動の典型的なものが、ヨーガの体操である。実際にヨーガの体操を行うと、体が温まってくることを多くの人が体験する。
※参考文献1
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/science_160222.html
※参考文献2
https://yab.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/sports_121203.html
※参考文献3
https://athleterecipe.com/bukatsubento/column2018/column08
※参考文献4
https://digitalpr.jp/r/35372
また、ヨーガには、体操(体位法・アーサナ)に加えて、呼吸法(プラーナーヤーマ)がある。呼吸法には様々なものがある。そして、その一部には、一定の規則で力強い呼吸を繰り返すことで体を温めて、新陳代謝と免疫力を促進する効果を持つものがある(※参考文献5)。
※参考文献5
https://gansupport.jp/article/life/exercise/exercise01/15732.html
3.ヨーガの各行法による精神的・生理的な効果
ヨーガとは、心の制御という意味であり、その行法は突き詰めると、心の制御・安定・悟りを目的としている。そして、免疫力に関しても、安定した前向きな精神が、免疫力を増大させ、逆に、ストレスが免疫力を低下させるという重要な事実が、医学的な研究で確認されている(※参考文献10・11)。
よって、心の制御・安定を目的とするヨーガの各行法の実践が、身体的な健康に限らず、精神の安定を助けて、心身の健康を共に増進し、免疫力の強化を助けることを示す医学的な研究結果も多く存在する(※参考文献6~9)。
※参考文献6:ヨーガの呼吸運動による免疫力の改善
https://www.futek.co.jp/achievement/pdf/yoganokokyuu.pdf
※参考文献7:ヨーガによる心理的な効果・精神の安定
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cou/44/2/44_110/_pdf
※参考文献8:ヨーガの心身への肯定的な影響
https://www.i-repository.net/il/user_contents/02/G0000031Repository/repository/keidaironshu_059_003_139-147.pdf
※参考文献9:ヨーガの心身への肯定的な影響
https://www.artofliving.org/jp-ja/%E3%83%A8%E3%82%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8A%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88
※参考文献10:ヨーガによる心身の健康・日常生活の改善
http://jssm.umin.jp/report/no36-1/36_1_08.pdf
※参考文献11:ポジティブな感情による免疫力の改善
https://psych.or.jp/interest/ff-01/
※参考文献12:ストレスによる免疫力の低下
https://www.min-iren.gr.jp/?p=2636
4.身体心理学の研究結果による知見
体の使い方と心の関係を研究する心理学を「身体心理学」という(その主導者は早稲田大学の春木名誉教授とされている)。その研究では、ヨーガで行われるタイプの体操や呼吸法、すなわち、筋肉を弛緩していく作業や、しっかりと長く息を出す呼吸法が、リラクゼーションを含めた様々な効能があることが確認されている。
例えば、筋肉を次第にほぐしていく体操は、リラックス効果を持ち、免疫グロブリンを増大させるという。免疫グロブリンとは、獲得免疫の一種である抗体を作る源になるので、これによって免疫力が高まることが期待される。
また、ヨーガの呼吸法のように、単に深呼吸するのではなく、吸ってから少し息を止めてゆっくり吐くこと(長い呼気)が、リラックス効果を持つことも確認されている。実際に、ストレスの表示とされるコルチゾールやPETCO2(呼気終末炭酸ガス分圧)の値が改善することが確認されたという。
さらに、ヨーガのアーサナ(体位法・座法)では、背筋を伸ばしたリラックスした姿勢で座ることが教えられるが、身体心理学でも、背筋を伸ばして、うつむきの姿勢を避けることで、前向き・ポジティブな心の状態になることが確認されたという。
さらに、ヨーガには発声法として、マントラ・真言と呼ばれるものがあり、その中には、「アー」音がよく含まれている。身体心理学でも、このアー音が、心を解放・安定させる生理的な効果があることが確認されているという。
なお、この身体心理学の詳細は、以下の参考文献を参照されたい。
※参考文献13
『身体心理学―身体行動(姿勢・表情など)から心へのパラダイム(新版)』春木 豊/山口 創編著、川島書店
※参考文献14
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20111013-OYTEW51530/
※参考文献15
ひかりの輪HP http://www.joyu.jp/hikarinowa/shrine/12/0063.html
5.ヨーガ・仏教の瞑想の精神的・生理的な効果
ヨーガ・仏教の源流において、「瞑想」とされる実践の重要な目的の一つが、心の安定である。前に述べたように、そもそも「ヨーガ」という言葉の原意が心の制御・静止であり、ヨーガ=心の安定(と集中)=瞑想ということもできるほどである。また、仏教で瞑想を意味する「禅定」という言葉の意味も、心の安定をもたらす修習と解釈されることが多い。
瞑想には、色々なタイプのものがあるが、それらは全て、正しく行うならば、精神の安定(と集中)をもたらすものである。そして、上記のマントラ・真言も、それを唱えることをマントラ瞑想といい、瞑想の一部と解釈することができる。
なお、瞑想の中で、大乗仏教・密教系の瞑想には、体温を上昇させる効果があるとされる(※参考文献13)。特にチベット仏教系では、熱のヨーガと呼ばれる瞑想もある。そして、前に述べた通り、この体温の上昇は、免疫力を高めることが知られている。
※参考文献16
http://blog.livedoor.jp/dogon23/archives/25488753.html
6.免疫の新しい考え方:自然免疫と獲得免疫
免疫力の強化を考える上で重要なことは、現在「免疫」の概念が大きく変わりつつあることだ。従来の古い免疫の概念とは、ある感染症に罹患して、その抗体ができることが、免疫があるか否かということだった。そして、実際に感染しなくても、同様の抗体を作り出せるのがワクチンというものであり、よって感染症対策の決め手になると考えられてきた。しかしこれは、すでに古い免疫に関する考え方である。
新しい免疫の考え方においては、冒頭で述べた通り、人の免疫力・抵抗力とは、①自然免疫と、②獲得免疫の二つがあって、その二つの総和が、その人の免疫力であるというものである。
そして、自然免疫とは、生まれつき備わっていて、どんなウイルスが体内に入って来ても、即座に機能する。一方、獲得免疫とは、あるウイルスが入って来た後にしばらくしてから、後天的に獲得されるものである。
そして、この獲得免疫の一部が、従来、免疫だと思われていた抗体による免疫である。この免疫のことを液性免疫ともいう(液体のように血中に溶けて存在するかららしい)。そして、これ以外に、キラーT細胞による免疫があり、これを細胞性免疫ともいう。
さらに、最近の免疫学においては、あるウイルスの感染でできた抗体が、それと似たウイルスにも免疫力を発揮する「交差免疫」や、何かのきっかけに免疫力が鍛えられて強化される「訓練免疫」という概念も出てきた。新型コロナウイルスの関係では、結核の予防のためのBCGワクチン接種が訓練免疫をもたらすのではないかという説もあるという。
よって、その人が新型コロナウイルスの抗体を持っているか否かを検査する「抗体検査」で陽性ではなくても(すなわち抗体を持っていなくても)、その人が新型コロナウイルスに感染した経験がないということは必ずしもできない。
というのは、自然免疫の方が、抗体という獲得免疫よりも先に発動するために、自然免疫によってウイルスを排除することができる場合は、抗体ができずに終わる場合があるからである。よって、抗体検査では、感染経験の有無はわからない。
さらに、抗体検査で陽性の人だけが、免疫を持っているわけでもない。場合によっては、抗体を作る必要さえないほど自然免疫(とキラーT細胞)が強い人の方が、抗体を持っている人よりも免疫が強いという場合もあるかもしれない。
また、新型コロナウイルスの場合にできる抗体は、寿命が短いのではないかという研究結果が少なくない。すると、感染して抗体を形成した経験がある人でも、感染からしばらくした後に抗体検査をした場合には、抗体が消失していて発見されない可能性もある。
しかし、そうした人でも、再度感染した場合には、自然免疫やキラーT細胞でウイルスを排除することができる可能性があるし、抗体に関しても、初感染の時よりも早く抗体を作ることができる可能性があるという情報がある。
さらに、重要なこととして、自然免疫の働きが強い人は、獲得免疫の働きも強いという。よって、全ての免疫の土台となるのは「自然免疫」と考えることができる。
※参考文献17:新しい免疫の考え方
https://www.asahi.com/articles/ASN6Y7W47N6YUCFI002.html
※参考文献18:T細胞による免疫
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93951.php
※参考文献19:T細胞による免疫
https://www.bbc.com/japanese/53266612
※参考文献20:交差免疫
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60554520Z10C20A6000000/
7.対策の要となるのは自然免疫の強化
こうして見ると、免疫力を強化する上で、その要となるのは、自然免疫の強化ということになる。その理由は、以下のとおりである。
第一に、自然免疫は、どんなウイルスに対しても即座に働く長所がある。一方、獲得免疫は、その時に感染した特定のウイルスに対して働く免疫であり、感染してから形成されるまでに、数日は要するとされる。これは、獲得免疫が、感染したウイルスに対して特化して形成される特異的な免疫力だからである。
これまでに新型コロナウイルスに罹患したことがない人にとっては、獲得免疫はまだ存在しないから、罹患した際に即座に機能するのは、現在は自然免疫だけである。罹患していない人が、抗体などの獲得免疫を形成するためには、ワクチンの開発を待たなければならない。
そして、これまでの感染状況を見ると、感染被害が大きい欧米はともかく、日本をはじめとするアジア諸国の多くでは、自然免疫が強いならば、無症状か軽症で済む人がかなり多いという可能性が指摘されている。
新型コロナは、高齢者や基礎疾患のある人の場合は重症化するが、こうした人たちは、自然免疫が弱っている。自然免疫は、一般に加齢とともに弱るとされる。逆に、若年層を中心に無症状ないしは軽症の感染者が多い。よって、この理由の一つが、自然免疫の強さだと推測されるのである(※参考文献21・22)。こうして、多くの日本人にとっては、新型コロナの感染と重症化の予防は、自然免疫の強弱が、その非常に大きなポイントだと思われるのである。
※参考文献21:自然免疫で感染を予防できている可能性
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/7-64_6.php
※参考文献22:自然免疫で感染を予防できている可能性
http://www.japanendovascular.com/covid-19_proposal_Ohki.pdf
第二に、自然免疫が強いと獲得免疫も強いからである。これは、罹患した場合に、獲得免疫が、早く・強く・長く機能する可能性があることになる。
前にも述べたが、新型コロナの場合は、感染しても、抗体ができるのが遅く、弱く、その寿命が短いという問題がある。しかし、自然免疫が強いと、獲得免疫も強くなるという一般則から見れば、抗体を含めた獲得免疫の遅さ・弱さ・寿命の短さ等の問題が和らぐ可能性がある。これは、将来的にワクチンが開発された場合でも、そのワクチンによってできる抗体の獲得免疫が、強くなる可能性があるということでもある。
8.ワクチンに過剰な期待をすべきではない
現在、米・英・中を中心として、新型コロナのワクチン開発が猛スピードで進んでいるという。米国の感染症対策のトップであるファウチ氏という責任ある立場の専門家が、今年末から来年頭にワクチン開発に成功すると考えることは合理的であるとまで明言する状況になっている。
しかしながら、世界保健機関(WHO)はごく最近、「新型コロナウイルスに対する完璧なワクチンという『特効薬』が開発されることは永久にない可能性があり、正常化への道のりは長いと述べた。」「効果的なワクチンが開発されないことへの不安がある。開発されても数カ月ほどの限定的な効果であるとの不安もある。臨床試験が終わるまでは分からない」と発表した(https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/who-78.php)。
この背景としては、①臨床試験は未了であること、②新型コロナの抗体の特性から見て、ワクチンができても効果的ではなかったり、効果のある期間が限定的であったりする可能性があるということである(※参考文献23参照)。
具体的にいえば、抗体は、善玉抗体と、悪玉抗体と、役無し抗体があるとされる。悪玉抗体は、逆に症状を悪化させる。これはADE現象といわれる。すなわち効果がないどころか副作用のある危険なワクチンになる。役無し抗体は、免疫にならない。例えば、エイズについては、30年経っても、まだワクチンはできていない。
さらに、善玉抗体ができたとしても、その抗体による免疫の寿命が短い可能性がある。この場合は、わかりやすくいえば、何度も接種しなければならなくなる。一方、WHOが「永久にできない可能性がある」とする「完璧なワクチンという特効薬」とは、一度接種したら一生感染しないようなもので、天然痘やはしかのワクチンは、完璧なワクチンである。
一方、インフルエンザは、すでにワクチンが開発されているが、毎年冬の前に接種するように、寿命が数カ月と短い。さらに、接種すれば完全に予防できるものではなく、感染・重症化の可能性を低くするものである。肺炎を起こす主因である肺炎球菌感染症のワクチンも、同じように可能性を低くするものである。こうしたワクチンを日本の免疫学の権威である阪大の宮坂昌之教授は「弱いワクチン」という。
よって、私たちは、ワクチンに関して、以下のような問題を抱えている。
①今年末から来年頭には、何ら効果のあるワクチンが全くできない可能性
②できたとしても、効果が弱いワクチンしかできない可能性
弱いワクチンは、何度も接種が必要なため、大量に安く生産できる技術も必要。
(経済力のある先進国は購入できても途上国には普及しないかもしれない)。
③より強い(ないし完璧な)ワクチンの開発には、さらに長い時間が必要な可能性
最悪の場合、強い(ないし完璧な)ワクチンは最終的にできない可能性
などを考慮しなければならない状況にある。
そうした視点から、高橋教授や宮坂教授は、一部の人は、自然免疫だけで新型コロナの感染を予防している可能性を指摘し、自然免疫を強める重要性を指摘し、いましばらく新型コロナウイルスと共存していく心構えの必要性を説いている(※参考文献23)。
※参考文献23
https://digital.asahi.com/articles/ASN6Y7W47N6YUCFI002.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/7-64_6.php
https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20200516-00178807/
https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20200517-00178891/
9.新型コロナとの共存とは何か:その厳しくも重要な現実を直視
皆が今、新型コロナウイルスとの共存を主張する。しかし、「共存」という言葉が先行していて、その具体的な意味は、必ずしも明確ではない。率直にいえば、最初は緊急事態宣言で外出自粛・休業要請をしたものの、経済的な問題で続けることはできず、経済活動を再開せざるをえなくなった時から「共存」ということがいわれ始めたと思う。
しかし、いざ経済活動を再開してみると、同時に検査を拡大したこともあり、死亡者・重症者は急増していないものの、PCR検査で陽性と判明した人の数は、過去最大となった。第一波の時とは検査数が異なるので、実際に今が過去最大の感染者数なのかはわからないが、入院者が急増し、重症者もじわりと増えてきたのは確かな状況の中で、目指すべき新型コロナとの共存の、具体的な意味が問われていると思う。
具体的な「共存」の意味の候補としては、医療崩壊を起こさない範囲で、一定数の感染者を受容して、経済活動の停止なしにやっていく社会を作るということだろう。そして、最もわかりやすい表現としては、すでに人類社会が共存しているということができる季節性インフルエンザや、肺炎を引き起こす肺炎球菌感染症といった既存の感染症と同じように扱っていくことだと思う。
そして、その前提として、WHOや専門家トップ(例えば前出の阪大の宮坂教授)が、すでに言い出しているように、新型コロナのワクチンがインフルエンザのように完璧なワクチンにはならず、弱いワクチンに留まる可能性があることだ。インフルエンザは、毎年接種が必要で、肺炎球菌のワクチンは、寿命が5年とされる。
さらに、インフルエンザは変異するので、多種のワクチンの開発とその接種が必要である。現在4種のワクチンを同時に接種している。新型コロナも、感染が拡大する中で変異をしているので、将来的にはインフルエンザと同じように、多種のワクチン開発が必要になるかもしれない。
そして、現在、結果として、毎年、インフルエンザを直接の死因とする死亡者が3千人強、インフルエンザをきっかけに肺炎などの別の病気になって死亡する人を含めた、インフルエンザ関連死を含めると、約1万人が死亡していると推計されている。また、肺炎球菌は、毎年約10万人が死亡する肺炎の二割弱の原因になっている。いずれも死亡するのは、高齢者が約9割だという。
だとすれば、新型コロナとの共存とは、単に医療崩壊を防ぐだけではなく、感染した場合に重症化・死亡する恐れがある感染弱者の保護に最大限努めつつも、インフルや肺炎球菌と同じように、一定数の死亡者は社会として受容することを意味することになるのではないだろうか。
一定数の犠牲者が出ても、インフルや肺炎のように経済活動を止めないということは、交通事故で毎年数千人の死亡者が出ても、車両の使用を止めないことと同じというと、わかりやすいかもしれない。止めるメリットより止めるデメリットの方が大きいからである。
10.死者を最小限にするために必要なバランスと諦観
これに関連して、今後予想されるやむを得ない新型コロナ死亡者数が、インフルや肺炎球菌や交通事故の死亡者数と比較して、どのくらいのものになるかがポイントとなる。これを試算したのが高橋泰教授である。
教授は、欧米では、すでに広く感染が広がっていることや、最近感染が判明した日本人の多くが無症状や軽症であることから、すでに数割の日本人は、新型コロナの感染を経験しているが、自然免疫等で感染を排除していると推定した。そして、今後予想される新型コロナウイルスの死亡者数は、毎年のインフルや交通事故の死亡者並みの3800人と試算した(※参考文献24)。
高齢者中心に、インフル関連で毎年1万人、肺炎で毎年10万人が死亡し、癌・脳血管疾患・心臓病では、それよりはるかに多くの人が、高齢者を中心に死亡している。一方、新型コロナ対策で経済が悪化して、失業者が増えれば、自殺者が増えるという見方もある。過去の統計データから試算すると、失業者1%増に対して数千人の自殺者増となるという。
さらに、異なる感染症には同時にはかからないというウイルス干渉という現象がある。今年のインフルの感染者は例年に比べて大幅に少なかったが、京大の上久保教授によれば、それは新型コロナの流行によるという(※参考文献25)。そして、今年前半の日本の死亡者総数は平年を下回っている(※参考文献26)。よって、今年は、高齢者を中心にインフルで死亡する人は少なく、新型コロナで死亡した人が出たが、総数は例年よりも少なかったことになる。
こうした状況の中で、現場の医師の中にも、「今回の新型コロナ問題に関しては、高齢者の死亡原因が新型コロナに変わるだけではないか」という見方をする人もいるという。少々乱暴な見方であるだろうが、新型コロナによる死亡者を減らそうとするあまり、不景気による自殺が増えてはいけないことは確かだし、現場の医師からすれば、新型コロナ対策の結果として、別の病気の治療が滞り、別の重症者・死亡者が増大するという懸念があるという(※参考文献27)。
※参考文献24:高橋泰教授の試算
https://toyokeizai.net/articles/-/363402
※参考文献25:上久保誠人教授の見解
https://diamond.jp/articles/-/238988?page=7
※参考文献26:今年前半の死亡者数
https://gemmed.ghc-j.com/?p=34726
※参考文献27
https://www.landerblue.co.jp/51382/
http://agora-web.jp/archives/2047170.html
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/61429?page=3
よって、社会全体としては、全体の重症者・死者を最小限にするために、新型コロナとともに、他の、同様に重要な分野とのバランスも図る必要がある。そのためには、どうしても「人は必ず何らかの原因で死ぬものである」という諦観(ていかん)が必要となってくる状況ではないだろうか。バランスを失えば、逆に被害を大きくしてしまうのである。これは、仏教も説く無常観につながる面があると思う。
11.今こそ根本原因について考える必要性
こうした厳しい状況にあるが、だからこそ今、この問題の根本原因について、あらためて考える必要があると思う。新型コロナウイルスのような新型の感染症が、この50年ほど前から発生し、今世紀に入って続発している根本的な原因はなにか。
その原因の一つは、現代社会が、その経済的な利益のために、無秩序な自然開発や野生動物の売買をしたことであるとされる。人間に自分の生息地を奪われたコロナウイルスが、変異して人間の体を新たな住処としようとしたのである(さもなければコロナは絶滅することになる)。
個々の犠牲者の方の存在は、大変痛ましいことであり、その回避のために最善を尽くすべきであることはいうまでもない。しかし、人類社会全体としては、新型感染症の反省に関して、人類社会側に大きな原罪があると考える必要があり、天が作った不条理とはいうことができないだろう。
そして、その反省としては、社会全体としての反省と、個々人の反省があると思う。まず、社会全体としての反省は、経済的な利益ばかりを追求した、無秩序な自然開発を反省して、それを最大限抑制することだろう。
加えて、新型コロナの感染被害は、個々人の健康状態・免疫力によって、大きく異なることが推測されている。よって、個々人としては、過剰な快楽の追求のために、不健康な生活習慣に陥って、自然免疫の低下を招いてこなかったかを反省する必要があると思う。個々人が、なるべく健康的な生き方・生活習慣に努めることが、個々人の感染予防と同時に、社会の感染拡大を抑制する助けになる。
そして、こうして見ると、新型コロナが教えることとして、社会と個々人のあり方が、新型感染症の発生・流行・被害と、密接不可分に関わりあっている世界に私たちは住んでいるということではないだろうか。
12.無秩序な経済活動と新型インフルの問題
先程も述べたが、新型感染症の続発の根本原因は、経済的な利益に偏った無秩序な経済活動である。その点を改めることなく、ワクチン開発などによってのみ問題を解決しようとすることは、非常に重大な問題を残すことになる。その一つが、新型コロナ以外の新型感染症の発生の恐れであり、もっと現実的な脅威とされるのが、新型インフルエンザである。
中国は、SARSのコロナウイルスの問題が起きた後に、野生動物売買の規制を緩めてしまい、今回の新型コロナ問題の発生に至ったともいわれているが、今年に入って、同じ中国で、新型の鳥インフルと豚インフルの発生が確認されている(※参考文献28)。未だ人から人に感染するような変異には至っていないが、人から人へ感染するようになれば、新型コロナと同じようにパンデミックになりかねないという。
そして、政府専門家会議の押谷教授は、新型コロナの次は、必ず新型インフルが来ると明言している(※参考文献29)。新型コロナは、一部では、100年に一度のパンデミックともいわれることがある。しかし、科学的に新型感染症の発生原因を見るならば、新型コロナが、今世紀の最後のパンデミックとなるとはいえない。
発生が懸念されている新型インフルは、鳥や豚から人に感染するという。すなわち、家畜産業が関わっている。中国に限らず、アジアの途上国では、急速な経済成長の中で、食肉の需要と生産が急増することが予想されている。
そして、新型感染症の発生を抑制するための安全対策がなされなければ、生産量が増大すればするほど、ウイルスが変異する可能性は増大し、新型感染症の発生の確率が増大する。しかし、その安全対策が、アジア地域の途上国を中心として不十分であることを最近も専門家が警告している(※参考文献30)。
さらにいえば、一定の肉食は、健康増進に役立つが、欧米と同じまでに消費が増えるならば、欧米と同じように、肥満・メタボの人が増大する。その結果、感染症には弱くなる。これは、新型コロナの感染でもすでに確認されており、肥満は新型コロナの重症化のリスクを増やす(※参考文献31)。
よって、個々人の消費者も、新型コロナの感染予防を含めた自分の健康と、さらなる新型感染症の発生を抑制する世界全体の安全という双方の目的のために、自分の食生活習慣の偏りを見直すべき状況にあるのではないだろうか。
※参考文献28:中国での新型鳥インフルや豚インフルの発見
https://www.asahi.com/articles/ASN7162KBN6ZULBJ013.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/02/post-92298.php
※参考文献29
https://nk.jiho.jp/article/p-1226551445258
※参考文献30
https://www.risktaisaku.com/articles/-/21388
https://www.risktaisaku.com/articles/-/21757
https://www.risktaisaku.com/articles/-/22302
https://www.risktaisaku.com/articles/-/22588
※参考文献31
http://www.seikatsusyukanbyo.com/main/opinion/003.php
13.性風俗産業等の問題
6月以降、いったん収まったかに見えた感染が、東京などの大都市を中心に再び増え出した。その発生源として問題となったのが、政府・自治体による感染予防対策や検査の要請に応じない、性風俗・キャバクラ等の夜のお店(以下「性風俗」と記す)の事業者であるといわれている。そのために、最近は、小池都知事や菅官房長官などが、休業を強制できる罰則を設ける法改正の必要性に言及している(※参考文献32・33)。
考えて見れば、30年ほど前に大きな犠牲者を出したエイズの時にこそ、性風俗はまさに重要な感染源になっていた。エイズはもっぱら性交で感染するからである(飛沫感染とか接触感染では感染しない)。しかし、この問題は解決されることなく、性風俗でのエイズ感染は続いてきた。
これは、エイズの特効薬ができたからかもしれない。しかし、特効薬はエイズを治すことはできず、症状を抑えるだけで、一生飲まなければならない。お金のない途上国を中心に毎年100万人が犠牲になっている。その意味で、エイズの時に解決していなかった問題が、今回の新型コロナでぶり返したということができるかもしれない。
そして、テレビの報道では、皮肉にも、政府からの給付金を握りしめて性風俗に行った若者もいるという。お金がなくて行けなかった人が、給付金をもらったからこそ行ったとしたら、感染症の抑止から見れば逆効果になったことになる(※参考文献34・35)。
このように、新型コロナ対策のために経済が打撃を受けたといっても、何でもかんでも経済活動を再開すればよいわけではないだろう。そもそも無秩序な経済活動が、新型感染症の発生と拡大の原因となってきたのであるから、これは当然といえば当然である。
※参考文献32
https://www.asahi.com/articles/ASN7H4K76N7HUTIL010.html
※参考文献33
https://www.sankei.com/politics/news/200719/plt2007190005-n1.html
※参考文献34
https://www.landerblue.co.jp/51286/
※参考文献35
https://www.landerblue.co.jp/49822/
14.過剰な欲望と無秩序な経済活動の制御が重要
新型感染症は、人の過剰な欲望に基づく無秩序な経済活動が招く人災の側面がある。この根本的な原因の解消を避けながら、政策やテクノロジーに依存して問題を解決することは、本質的にできないのではないか。やはり、個々人と社会全体が、欲望と経済活動を制御する知恵と力を深めていかなければならないだろう。
今問題になっている政府のGoToトラベルキャンペーンに関しても、政府専門家会議の尾身(おみ)氏も言っているように、旅行の移動が悪いのではなく、移動先で、感染を広げるような行動をとるのが問題である(※参考文献36)。例えば、東京に来て何をやるか、地方に行って何をするのかが問題である。しかし、それがきちんとできないと、県外への外出を一律に自粛するべきだという意見も出てくる。
このように、自己の行動を制御できない限りは、問題が続いていき、ゆくゆくは先ほど紹介したように、罰則によって、それを強制する法規が導入されることになるかもしれない。そして、こうしたことが繰り返されると、感染症(や戦争)のような非常時には、大幅に人権を制約する欧米型の「非常事態宣言」の法規の導入が必要だという流れが出てくるかもしれない(安倍総理が憲法の改正で狙っているという話もあった)。平時は自由主義だが、非常時は社会主義ともいうべき政治制度の導入である。
しかし、どんな人間も不完全であって、自己中心・独善性がある。そのため、社会主義国家の歴史を見ると、共産党幹部が、自己の問題を隠蔽し、健全な反対意見は弾圧し、富を独占して、資本主義以上の貧富の格差が生じているように思われる。
そもそも、今回の新型コロナに限らず、SARSや最近の新型鳥インフルや新型豚インフルの問題も、全て中国から発生している。最近は、新型コロナの発生源となった武漢を含めて、大規模な水害が発生している。その中で、巨大ダムの三峡ダムの決壊・崩壊が懸念されているが、このダムは、そもそも共産党体制による独断的な意思決定で、無理に作られたという情報もある(※参考文献37)。
新型感染症を続発させる自国の経済活動の在り方を十分に反省しないままに、経済・軍事・覇権の増大ばかりを追求しても成功はしないだろう。その欲望追求にともなう焦りなどから、何かの重大な問題、しっぺ返しが発生する可能性があると思う。
結論としては、新型感染症を続発させている国の政治体制が、問題を最終的に解決することはないだろう。大規模災害が発生した際に、政治体制を臨機応変に調整することは悪くはないかもしれないが、まずは一人一人が、問題の根本原因である過剰な欲望に基づいた無秩序な経済活動に向き合うことが肝心だと思う。
人類社会は、少なくともその一部において、ウイルスを含めた自然に対して、どこかで傲慢な戦いに入っているのではないだろうか。欲望を適切に制御できず、政策やテクノロジーに依存するばかりで、根本的な問題解決の道を歩むことができていないのではないだろうか。
※参考文献36
https://www.news24.jp/articles/2020/07/16/06681891.html
※参考文献37
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/07/---5.php
15.焦りと油断の双方に注意するべき
こうして新型コロナ問題の背景には、欲望の制御という、人類社会の心の問題があることがわかる。そして、心の問題に関連して、さらにいえば、こうした危機に際しては、焦りと油断の双方に注意するべきだと思う。
仏教の心理学を学んだ視点でいうならば、人が失敗するのは、①状況・調子が良くて舞い上がり、心が浮ついた時に生じる慢心・油断と、②状況・調子が悪くて心が落ち込んで、不安・恐怖・焦りが生じる場合のときが多い。言い換えれば、躁状態の時と鬱状態の時、頂点と底辺で失敗する。
さらに、心の浮つき・舞い上がりが大きい人ほど、その次に来る心の落ち込み・不安や恐怖も大きい。波の山が高いと谷も深い。浮ついている時は、良いことばかりを見て油断し、問題に対する注意・警戒が不足して、落とし穴にはまる。そして、落ち込んでいる時は、悪いことばかりを見て不安・恐怖が生じ、それから抜け出したいという焦りが生じて、ものを正しく見ることができず、空回り・逆効果・自滅的な行動をとる場合が多い。
そして、日本に関していえば、第一波に対して、欧米に比較すれば、非常に少ない死亡者数で抑え込みに成功した後に、多少なりとも油断したのではないかと思う。例えば、東京都が、第一波の終息から2カ月も経たないうちに、軽症者用に用意していたホテルを解約して、その直後に発生した第二波への対応に窮して、政府に批判されるといった問題もあった(※参考文献38・39)。
※参考文献38
https://mainichi.jp/articles/20200716/k00/00m/040/310000c
※参考文献39
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200801-OYT1T50168/
16.日本もまだまだ油断大敵との見解
この視点から、日本もまだまだ油断してはならないと考え、経済活動を再開しながらも、最大限の感染予防努力や、感染の再拡大に対する備えを続けるべきだと思う。その視点から、今後注意すべきと思われるポイントを挙げてみたいと思う。
第一に、今のところは、日本・アジアは、欧米に比べて被害が少ないが、今後、感染が拡大を続ける欧米などからの入国制限を解除する場合には、再び感染が拡大する問題がある。特に、感染拡大中の外国と、感染が比較的少ない日本・アジアの間で、入国制限の解除を巡って摩擦・外交問題が生じるという指摘がある(西浦教授など。※参考文献40)。
第二に、東大の児玉教授によれば、新型コロナは発生以来、様々な変異をしているが、東京は、中国の武漢やニューヨークとは異なり、その地域において特に拡大する変異株、すなわち、ローカルウイルスの感染拡大はまだ経験しておらず、これが、被害が少なかった原因である可能性があるというものだ(※参考文献41)。
しかし、最近の東京を中心として拡大を始めている新型コロナは、東京・埼玉株とでもいうべきローカルウイルスであり、「エピセンター」=「感染震源地」を形成し、非常に多くの感染者が発生する可能性があるという。ただし、同教授は、一日数十万人規模のPCR検査などの大規模な検査(と感染者の隔離)を実行すれば、封じ込めは十分可能であるともいう。
三つ目は、医療の専門ではないが、JETRO(ジェトロ)研究員の熊谷聡氏によれば、日本の感染被害が少なかったのは、地理的な有利性によるものだという。わかりやすくいえば、日本は武漢には近いが、その後イタリアなどに感染が広がり、ウイルスが変異して感染力が強まったものの、そのイタリアからは遠かったことが幸運だったということである(※参考文献42)。よって、東京のローカルウイルスで強毒のものが現れれば、事態は予断を許さなくなる。
※参考文献40:西浦教授の見解
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/06/8-39.php
https://toyokeizai.net/articles/-/352503
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/24088
https://toyokeizai.net/articles/-/362956
https://toyokeizai.net/articles/-/352744
※参考文献41:児玉教授の見解
https://johosokuhou.com/2020/07/17/34537/
https://blog.goo.ne.jp/sa-1223/e/272cdb4bc20c33617ed434359666b884
https://news.yahoo.co.jp/articles/6455d8ed1b4eef12418919210af12b92e7505fc0
※参考文献42:熊谷氏の見解関係の情報
https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Eyes/2020/ISQ202020_018.html
http://agora-web.jp/archives/2047039.html
17.油断ならない状況の中で重要な自然免疫の強化
日本・アジアは、欧米その他に比較して確かに感染被害が少なく、それは自然免疫などが強いためであり、これからも大丈夫だという意見もある。しかし、感染被害の違いの原因として挙げられているものは、今のところ科学的には仮説にすぎない。本当に自然免疫が強いのか、何かの幸運の結果なのかはわからない。
さらに、新型コロナも、インフルと同様に、絶えず変異を続けている。よって、この数カ月間は大丈夫だったからといって、今後も大丈夫といえるかは別である。100年前に世界で数億人が感染し、数千万~1億人の死亡者を出したとされるスペイン風邪のパンデミックでは、合計三波が発生したが、大半の死亡者は第二波以降であり、第一波の死亡者は少なかったという事実がある。さらに、第二波以降では、若者の犠牲者が増えており、その意味で、ウイルスの毒性が変化したと考えられる。
こうした不確実な状況の中で、私たちが、将来の安全のためにできる第一のことは、やはり「自然免疫の強化」だと思う。そのためには、食事・運動・睡眠などの、日ごろの生活習慣と、安定した前向きな心・精神状態の維持がいよいよ重要だと思う。