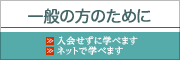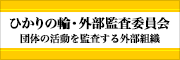哲学・科学・宗教:人類の叡智を総覧する
この章では、哲学、科学、宗教といった人類の叡智とされるもの全体に関して考察してみたいと思う。そして、これは、現代に生きる私たちが、常識として確かなものと信じているものが、いかに実際にはあやふやなものであって、現代も、近代や中世と変わらぬほどに、依然として発展途上であるということを知る手助けとなる。それは、いわゆる無知の知・謙虚さという偉大な智恵を与え、その結果として、真の智恵・叡智の進歩に役立つものだと信じる。
1.哲学とは何か
哲学の原語であるphilosophiaは、philein(愛する)と、sophia(知恵、知、智)が結び合わさったもので、「知(智)を愛する」、「愛知(智)の学」といった程の意味になる。なお、「哲学という日本語訳は、明治時代に西周(にし あまね)が用いて一般的に用いられるようになったという。
よって、何を研究する学問であるかは決まっておらず、物理学とか、医学などと違って、学問の対象が決まっていないのである。広辞苑によれば、哲学とは、以下のように定義されている。
「古代ギリシアでは学問一般を意味し、近代における諸科学の分化・独立によって、新カント派・論理実証主義・現象学など諸科学の基礎づけを目ざす学問、生の哲学、実存主義など世界・人生の根本原理を追求する学問となる。認識論・倫理学・存在論などを部門として含む」
(『広辞苑』第五版、岩波書店、1998年、「哲学」より)
すなわち、古代は、哲学は、学問一般であった。学問とは哲学であった。その後に、諸科学が哲学から分化・独立して、それ以外が哲学として残ったということである。
哲学のテーマは、一定していないが、よく扱われるものは、真理、本質、同一性、普遍性、数学的命題、論理、言語、知識、観念、行為、経験、世界、空間、時間、歴史、現象、人間一般、理性、存在、自由、因果性、世界の起源のような根源的な原因、正義、善、美、意識、精神、自我、他我、神、霊魂、色彩などがあり、抽象度が高い概念であることが多い。
また、その世界や物事や人間が、どのように存在しているかを論じる「存在論」と、「善とは何か(あるのか)」といったことを論じる「価値論」がある。
また、近年は、哲学といえば、今現在の課題を扱うというよりも、過去の哲学(の歴史)を研究する学問とされることが多い。例えば、ギリシア哲学、中世のスコラ哲学、ヨーロッパの諸哲学(イギリス経験論、ドイツ観念論など)の主題、著作、哲学者を研究の対象とする学問である。
2.さまざまな地域の哲学
ヨーロッパ哲学は、その大きな特徴として、「ロゴス(言葉,理性)の運動を極限まで押し進めるという徹底性」があり、古代、近代、現代といった節目を設けて根底的な相違を見出すようなことが比較的容易であるといえる。古代、近代、現代といった枠組みの中でも大きく研究姿勢が異なる学者、学派が存在する場合も珍しくない。
次に、東洋哲学についてであるが、哲学とは西洋で生まれたものだが、中国哲学、インド哲学、日本哲学というように、東洋思想を哲学と呼称する場合も多い。
インド哲学は、インドを中心に発達した哲学で、特に古代インドを起源にするが、インドでは宗教と哲学の境目がほとんどなく、インド哲学の元になる書物は宗教聖典でもある。よって、インドの宗教には、哲学的でない範囲も広くある。
中国哲学というと、老子や荘子の道家、孔子や孟子、荀子らの儒家、朱子学、陽明学がよく取り上げられる。
3.元は一体だった自然科学と哲学
哲学は、最初から、自然現象の説明に努力した。そもそも、19世紀までは、科学(science)や自然科学(natural science)という言葉ではなく、「自然哲学」(natural philosophy)ないしは「自然学」(Physics)という言葉が使われていたという。例えばニュートンの『プリンキピア』の正式名称は『自然哲学の数学的諸原理』である。
しかし、近代において、実験を重視する実験科学が登場すると、哲学と自然科学が分離し始める。こうして独自の研究方法が確立した分野が、哲学から分離して、諸科学となって、それ以外の分野について考えるのが哲学という感じになっていったようである。よって、哲学の研究対象として、科学的な研究方法が定まらない分野と、それに加えて、「どうあるべきか」「善とは何か」といった倫理や価値論の分野が残っていったということになる。
4.現在までの哲学と自然科学の相互作用
知・智を愛する哲学は、自然科学を無視することはなく、自然科学の新たな発見が、旧来の哲学を変化させたり、その逆に、古代の哲学者がなした科学的な知見が、自然科学の分野であらためて証明されたりすることもあった。
特に近代の哲学者は、自然科学者の成果を重視し、観察や経験を重要視する哲学者たちが生まれた。逆に、科学者たち自身が扱わないような非常に基礎的な問題、例えば、科学と非科学の区別などについては、哲学者が考察を行ってきた(科学哲学)。こうした哲学者の活動が、新しい科学理論の形を呈示した場合もあり、相互に影響を与えている面もある。
5.宗教と哲学:対立的な関係と類似性
哲学は、宗教と同様に、神の存在に関連している分野を含んでいる。そのため、両者の厳密な区分は難しい。ただし、それは科学と非科学の区別が難しいのと同じように、境界がはっきりしていないということであって、理性を重視する哲学とは明らかに異なる宗教と、理性を否定する面が強い宗教の区別は可能である。
そもそも、宗教哲学の項で述べるように、理性を重視する哲学は、その始まりから、理性を否定して盲信に陥る一面がある宗教に対して、懐疑的な姿勢を取ることが、その一つの役割であった。
そして、宗教や神の存在に関する知的な理解を求めた人々は、哲学的な追究をし、逆に信仰生活(実践)に重点を置いた人々は、理屈や議論を敬遠した面があったろう。
哲学と宗教との差異として、理性に基づく疑問・考察があるか否かがあげられることが多い。もちろん、宗教の中には、仏教のように哲学的で、師匠の見解に対する疑問・批判的な考察・改良を許してきた伝統があるものもあるが、信仰の遵守を求めるドグマ性があって、時として疑問抜きの盲信を要求しがちな面があるとして、比較される。
そして、西洋における哲学は、神話・宗教を母体とし、これを理性化することによって生まれてきたといった見方は、今日一般的な哲学観となっている。
6.宗教哲学の誕生
宗教哲学(philosophy of religion)は、18世紀末ごろにヨーロッパにおいて成立したもので、宗教一般の本質、または、あるべき姿を探求するとともに、宗教を理性にとって納得のゆくものとして理解することを目的とする。
前に述べたように、古代ギリシアなどで哲学が誕生した時から、それは、伝統的宗教に対する疑問と結びついていた。
哲学は、理性によって宗教を解釈し、捉え直そうとしていた。そして、近世になると、ヨーロッパで強まった理性の啓蒙は、キリスト教の伝統的な信仰や神学を批判する哲学の流れを作った。
その結果、二つの流れが生じた。一方では、宗教を理性によって否定しようという流れが生じ、一方では、その真逆に、理性を否定して、信仰の立場を維持・確立しようという流れである。これは、今現在の人類社会にも当てはまるかもしれない。いわゆる、宗教を否定する無神論の流れと、原理主義的・保守的な宗教に回帰する流れである。
7.第三の道としての宗教哲学
これに対して、第三の道が宗教哲学であった。それは、盲信を排除し、理性に基づいて、理性が納得いくように、宗教を新しく解釈し直そうとするものである。この立場を確立したのが、カントとされる。
「ひかりの輪」も、オウム真理教の一連の事件に直面した者たちが、それによって、宗教的なものをすべて否定するのでもなく、「アレフ」のように理性を否定して従来の信仰を続けようというのでもなく、理性を否定する盲信を排除し、理性の納得がいくように、宗教を再解釈して、宗教そのものではない、新たな人の幸福の思想・哲学を作り上げようとする点で、この伝統的な宗教哲学の発生と似ている面がある。
ヨーロッパでは、カントが「単なる理性の限界内での宗教」において、キリスト教の信仰の内容について、それを道徳という実践理性の立場から解釈して、キリスト教の説く真理を人間の普遍的な真理として再解釈しようとした。こうして、彼は、宗教を人間にとって普遍的な意味を持つものとして再解釈する宗教哲学への道を開いた。
その後、カントのように宗教を道徳の範疇でとらえるのではなく、シュライアマハーのように、「宇宙の直観」などと見たり、ヘーゲルのように「生の根幹」ととらえたりする見方が現れたが、いずれにしも、宗教を理性に基づいて理解するものである。
8.「ひかりの輪」の基本理念
さて、ここで、以下に、「ひかりの輪」が、昨年制定(改正)した団体の「基本理念」(団体の綱領)の一部を紹介する。
………………………………………………………………………………………………………………………………
「ひかりの輪」基本理念
1, 思想・哲学の学習・実践を通じて、社会への奉仕に努める
私たちは、物心両面の幸福のための様々な智恵・思想を学ぶとともに、現代に合ったものを新たに創造・実践し、普及させていく。物の豊かさに限らず、心の幸福・豊かさ・解放・悟り、真の自己実現・人生の目標の達成、さらには21世紀の社会全体の幸福の実現を通じて、社会への奉仕に努めていく。
そのために、私たちは、仏教などの東洋哲学や心理学をはじめとする東西の思想哲学を学習・実践していく。その対象には、仏教のほか神道、修験道、仙道、ヨーガ、ヒンドゥー、聖書系等の宗教の思想哲学を含んでいるが、私たちは、特定の教祖・神・教義を絶対視して盲信したり、人や自然とは分離された超越的な絶対者を扱ったりすることはないので、宗教または宗教団体ではない。
また、学びの対象には、宗教思想とともに、心理学、物理学などの自然科学、社会学、人類学、国内外の歴史なども含む。
2, 宗教ではなく、「宗教哲学」を探求していく
一般に宗教とは、「神または何らかの超越的絶対者、あるいは卑俗なものから分離され忌避された神聖なものに関する信仰・行事」と定義されており(※1)、その実践においては、崇拝対象に対する疑問や理性による考察を許さない絶対的な信仰や、行きすぎた盲信を伴う場合もある。
しかし、私たちは、次項以降に述べる理由により、特定の存在に対する絶対視や盲信を否定するとともに、人間から分離された超越的絶対者を崇拝することなく、理性を十分に維持して、私たち自身の内側や周辺の現実世界の中に神聖なる存在を見いだして尊重していく実践を行う。
これを正確に表現するならば、「宗教」ではなく、「宗教一般の本質ないし、あるべき姿を自己の身上に探求し、理性にとって納得のゆくものとして理解しようとする」とされる「宗教哲学」(※2)の実践といえるものである。
(※1)岩波書店『広辞苑』
(※2)岩波書店『岩波 哲学・思想事典』
………………………………………………………………………………………………………………………………
9.宗教哲学の本質:理性と感性のバランス
こうして、崇拝対象に対する疑問や理性による考察を許さない絶対的な信仰や、行きすぎた盲信を伴う場合もある「宗教」に対して、宗教哲学とは、宗教を理性にとって納得のゆくものとして理解・解釈するものということができるだろう。
わかりやすく言えば、人は、神的なものを感じる体験をする場合があると思う。しかし、自分が感じたことが、本当に神そのものなのか。それは、あくまでも自分の中の神体験であって、本当に自分を超えた絶対者・超越者である神を体験したのか。
人は、そもそも外界の存在を直接的に体験するのではなく、自分の中の脳内現象を体験しているのではないか。こうした、客観的な、合理的な視点から、自分の感じたこと、体験したことを検討するのである。
10.「感じること」と「存在すること」の違い
人間が「感じること」と、実際に「存在するもの」は同じではない。これは、実は、ほかでもない仏陀の教えのエッセンスである。その意味では、仏教は、宗教とされながら、その中には、一般の人が宗教に抱くイメージとは真逆の要素、非常に哲学的、科学的な視点を含むものである。
話を元に戻すと、人が、五感と意識、五感と言葉による思考によって把握するものは、厳密に考察すると、物事が実際に存在するあり方とは、実際には大きく異なっていることが多い。
その良い例が、地動説と天動説である。日常の感覚では、どう見ても、太陽が地球の周りをまわっているのだが、科学の発見は、その逆であることを立証し、その土台の上に、現在の宇宙関連技術は機能している。こうして、科学の発展は、人の感性と異なる世界の真実を示してきた。
分子生物学の発展は、常識的な人間観も覆している。普通に他人を見ると、自分とは別の生きものに見えるが、自分と他人は、それぞれが吐き出した空気をそれぞれが吸い込んで、それぞれの体を構成する分子を共有している。すべての生命体は、地球生命圏を循環する分子を共有し、一体となっており、「体を共有している」のである。
11.感性の究極:「神のようなもの」を感じること
しかし、人は、非常に多くの場合、自分が感じたことに基づいて生きるものだと思う。そして、その感性の究極が、「神のようなもの」を感じることだと思う。人類の歴史を見ると、宗教は人類の文化・社会・国家の中核にあり、無数の宗教が生まれた。ここ数世紀いろいろな意味で世界をリードしてきた欧米社会は、キリスト教社会であり、中世まではキリスト教が絶対であった。
戦後日本は、国家神道による戦争の反動で、無宗教と自覚する人が多いが、宗教に属さずとも、節々でお寺や神社には足を運んでお祈りをし、世論調査では、人間を超えた大いなる何かがあると思う人が、無いと思う人より多いという。これは、特定の宗教に特化しない、日本人独自のやわらかく高度な宗教心であり、未来の人類のスタンダードだという主張もある。もちろん、戦後も無数の宗教団体が生まれ、活発に活動しているし、そもそもが、国家神道による戦争でさえ、まだわずか70年前のことだ。
欧米の先進国は、政教分離の原則があるが、政治・国家運営の世界にも、宗教の大きな影響がある。米国大統領は、その就任の宣誓式を「それ故に神よ、私を助けてください」という言葉で締めくくる。宗教こそ、人と動物との違いだという考え方もある。戦後、猛烈な労働で経済を発展させた日本人は、エコノミックアニマルと揶揄されたこともある(なおエコノミックアニマルとは経済に非常に優れた才能があるというほめ言葉という解釈もあるが)。
12.感性の暴走:盲信
そして、時には、感性が暴走する。感じたものが感じたとおりに確かに存在すると考えて、客観的に見れば(多くの他人から見れば)、理不尽な形で、他人を傷つける。
「ひかりの輪」が、反省と教訓の対象とするオウム真理教事件は、教祖と信者が感じた「神のようなもの」が、客観的で合理的な根拠がないにもかかわらず、真理だという集団心理が形成されて、起こされたものであった。
イスラム原理主義、イスラム国の宗教的な戦争もそうだし、日本こそが神の国だと信じた大日本帝国の戦争にもその一面があるし、欧米の植民地侵略も、キリスト教を唯一絶対の真理と信じて、武力をもってしてでも世界に広めようという一面があった(牧師が軍隊と一緒に侵略した)。
13.感性の暴走を止める理性
だとすれば、我々は、感性の暴走に対して歯止めをかけようとする意識を持つ必要がある。感性に対して、理性といえばいいだろうか、客観的・合理的な思考によって、感じたことが実際にそうであるかを検証するのだ。
その結果として、感じたことを完全に否定することになる場合もあるだろうが、少なくとも、疑問符をつけて、保留扱いにすることもあるだろう。少なくとも保留扱いにすることができれば、暴走することがなくなる。それは、感じたことを絶対視するのではなく、相対化することである。
14.人は神を知る能力があるか
神のようなものを感じる人の感性に対して、理性による疑問は、たとえば、以下のようなものである。
人間は、不完全で全知には程遠く、宇宙のごく限られた範囲しか知らない。完全で全知で宇宙全体に存在するとされる神というものが仮に存在するとしても、それを知ることができるだろうか。神を知ることができるものは神だけであって、神でない者が、神を知ることができるだろうか。
たとえるならば、バクテリアのような微生物は、人間を理解できるだろうか。サルと人間の違いを理解できるであろうか。犬や猫と人間の違いはどうか。昆虫と人間の違いさえ危ういのではないか。そして、動物や昆虫と、人間を取り違えれば、いったい何が起こるか。次元が違う者は、正しく理解できない可能性の方がずっと高いのではないか。
15.否定の断定も不合理:理性の暴走・独裁
しかし、だからといって、神が存在しないというわけではない。あくまでも、人の能力では、神が存在するかどうか、わからないというだけだ。神が存在しないと知ることも、神(を超えた神)でなければできないだろう。感性の暴走を抑制する理性の働きとは、感性を相対化することであって、わからないものは、わからないままにすることである。
仮に、わからないから、証明できないから、存在しない、と断定することではない。もし存在しないと断定してしまうと、それは、逆に、理性の暴走・理性の独裁となる。感性の絶対性を否定するのはよいが、その反動で、理性を絶対とすれば、同じ愚を犯すことになる。人間は不完全であり、現在の科学さえも不完全であって、発展途上にほかならない。
にもかかわらず、自分たちがわからないことは全て存在しないと決めてしまうことは、わからないことを確かに存在すると盲信することと、本質的には、同じ愚である。両者とも、無知の知の謙虚さと、それに基づく継続的な探究心を失っている。
そして、理性に基づいて宗教を理解・解釈しようとした宗教哲学に対して、近年、理性ではそもそも理解できない神と宗教を理性で解釈しようとすることは矛盾しているという批判がある。これも、理性の独裁が起こった時に生じる批判ではないかと思う。何事も行きすぎは問題である。
16.理性の限界を突破する感性
科学の発見も、最初は、感性の働きから生じる場合がある。科学が、夢で見たものとか、合理的な根拠はないが、直感的に感じたことなどから生じる場合である。発見・発明とは、それまでにないものを見つけることだから、それまでの常識・知識・概念では理解できないことが多い。
最近も、ノーベル賞を受賞した中村修二教授は、「ノーベル賞はだれか"狂ったこと"をしてこそ取ることができる。大きな企業には多くの上司がいるから、奇抜なアイデアが最後まで生き残ることはできない」と断言したという。
例えば、今現在は、近代の自然科学の幕開けとして不動の地位を得ている、アイザック・ニュートンの万有引力の法則も、発見当時は、十分には理解されずに、「オカルト」とされたことがある。最初は、非科学・まやかしとされたことが、後に科学と認められた事例も少なくない。ガリレオの地動説もそうだっただろう。
すなわち、理性・合理性の働きは、従来の知識・概念に基づいて推察するという限界がある。だから、理性ばかりに偏り、感性を一切無視すれば、従来の知識・概念を突破して、未知の真実を知るきっかけを失う可能性がある。それは、進歩・進化を阻むことになる。
17.理性と感性のバランス・調和
そうすると、結論としては、理性と感性のバランスが必要なのではないかと思う。感じたことはすべて存在するとしてしまう「感性の暴走」と、わからないことはすべて存在しないとする「理性の暴走」という二つの暴走を回避して、感性と理性のバランスをとることである。
感じたことをすぐに存在すると思い込まずに、理性によって検証してみる。そして、従来の枠組みで直ちに理解できなくても、感じたことをすぐさま否定しない。わからないことはわからないとして、あるともないとも決めつけずに、さらに探究を続ける。無知の知に基づく、継続的な探究心である。
そのため、「ひかりの輪」の基本理念では、宗教哲学の項目の後に、「自己を絶対視せず、『未完の求道者』の心構えを持つ」「私たちは、謙虚に、自らを『未完の求道者』と位置づけ、道を求め続けていく。」としている。
そして、理性で宗教の感性の暴走を止めようとした宗教哲学も、理性の独裁ではなく、理性と感性のバランスの上に実践されてこそ、その真の価値を発揮すると思う。
18.科学と非科学の区別とは
以上と関連することとして、科学と非科学は区別できるのか、について検討しておきたい。というのは、科学と宗教は、一部の人にとって、よく対極的なものとされるが、この場合は、それは、科学と非科学とはほとんど同じことのように扱われるからだ。
しかし、結論から言えば、科学と非科学の区別を研究する学問である科学哲学の検討の結果は、両者の境界はあいまいであって、両者を区別する基準は確立できないというものである。
まず、科学的であることの基本原則は、実験的な結果が再現可能であり、他者が検証可能ということである。STAP細胞は、小保方氏以外の研究者によって再現ができなかったので否定されたのである。そして、科学哲学者のカール・ポパーは、反証が可能であるという意味の「反証可能性」を持つ理論を科学とした。「反証が不可能」な理論は、科学ではないとして線引きされる、という考え方である。
しかし、現場の科学者たちは、1度でも反証された理論を破棄するかというと、実際にはそうではないと指摘されている。科学者の実態は、ある理論が採用される・されない、というのは、合理的な論理によってではないという。実験を行った結果、彼らの意に反して反証された場合、それを素直に認めることはなく、自分たちが信仰している中心的な命題を守りたがり、実験のほうが失敗だったと解釈したりする。
しかし、科学の世界では歴史的に見て、ある時代に当然だと認められている命題が、後代になってあっけなく覆ってしまうことが何度も繰り返されてきた。そして、そうした時に、信仰されてきた理論体系を打ち倒しているのは、別の理論体系を提唱した別の科学者集団である。
19.科学界も歪める集団心理
「集団心理」と言うが、「多数派の意見に追随して安心したい」とか、「少数派になることは怖い、」という心理・バイアスがかかり、行動・言説が変化してしまうということが明らかにされている。
科学者も科学界という閉鎖的な集団の場で活動している人間であるので、その例外ではなく、ある科学者の集団(学会など)である理論体系を採用する人が多数派になると、それによってバイアスがかかり、それに追随したいという心理が働き、別の説は支持しにくくなるという心理が働く、ということが指摘されている。これは、まさに宗教団体にも通じる構造である。
また、さらには少数派の説を非難することで自分が多数派に属していることを誇示することでバッシングに合わないようにする心理が科学者にも働くという。学校の教室のいじめの行動、および、いじめられ回避の行動と似ている。宗教団体でも同様である。
20.統計とバイアス:プラシーボ効果
反証主義以降に、ある頻度で起こるというように確率的にものごとを検証する方法としての統計学が発達していったが、この場合も、人間の心理的な原因によって、バイアスが起こり、例えば、自分の都合のいいように証拠を集めるバイアスもある。
こうしたことを避けるため、観察者にも誰に偽薬を渡したのかわからない計測方法である二重盲検法が導入された。そして、偽薬や偽治療によっても心理作用によって効果が出るというプラシーボ効果が発表され、従来認められていた効果が単なるバイアスやプラシーボ効果である可能性が指摘されるようになった。
こうした中で、2000年以降は、医学の分野では根拠に基づいた医療(Evidence Based Medicine)が大きく展開され、統計的な有効性といった科学的根拠に基づいた診療ガイドラインが作成されるに至った。
21.科学界と産業界のつながり
業界の利益を脅かすような問題が起きると、業界団体がその問題の研究を始める例が、ここ30年間で非常に増えている。 例えば、ある企業の従業員が危険なレベルの化学物質にさらされていることが研究から明らかになったとしよう。
そういう場合の企業の典型的な対処法は、自社で研究者を雇ってその研究を批判する研究をさせることだ。また、ある薬の安全性が取りざたされると、製薬会社の経営陣は健康に対する深刻な危険はないとする実験結果をさかんに宣伝する。この手の研究は会社の資金で行われ、不安を感じさせるような結果は無視したり隠したりする。
米国産業界の一部では脅威となる研究を「ジャンクサイエンス(ニセ科学)」だと非難し、反対に業界が委託して行った研究を「サウンドサイエンス(健全な科学)」として正当化することが常套手段になっている。
22.疑似科学による悪徳商法、宗教の霊感商法
疑似科学は、悪徳商法と親和性が高い。特に、偽医療の分野に親和性が高く、療法の根拠として使われることがある。世間に広く知れ渡っている医学的俗説の中には、医学的な正当性がないにもかかわらず医師がこれを信奉しているものもあるため、不適切な医療行為の原因になる恐れが指摘されている。
そして、これは、宗教団体・精神世界関連団体でも批判される霊感商法と構造は同じだろうと思われる。どちらも、例えば、健康問題や悪霊憑依など、何かの実在しない危険性を訴え、それに対して、必要のない解決策(健康食品・健康機器・悪霊払いの儀式)を勧める。
23.宗教界と科学界の類似性質
こうして、科学界も宗教界も、双方とも人間が行うことであるから、そのグループの中の最高権威(教祖)や主流の考え方(教義)になびく集団心理、個々人の名誉欲・権力欲、さらには金銭欲といったものが、宗教と科学の区別を問わずに、働いている。
そのために、宗教と科学は、双方が、「真理の探究を本来の目的としている」と主張し、そして、お互いがお互いに関して批判的な主張をする場合が少なくないにもかかわらず、客観的に見ると、そうした主張に矛盾して、様々な共通の問題を抱えている現実がある。
24.違いとつながり:二分化していないが違いはある
しかし、当然のことであるが、明らかに科学的であるものと、明らかに非科学的であるものの区別は当然可能である。すなわち、両者の違いは明確だが、両者にはつながりがあると言えばいいだろうか。
これは、宗教と哲学の区別についても、同様であって、両者の境界を定めることは困難だが、理性を重視して宗教の盲信に対抗する哲学に対して、人間の理性を否定しても神を信じようとする宗教があるように、両者の違いは明確である。
哲学と科学、哲学と宗教、科学と宗教といった、一見して対極的な両者の関係は、実際には、白と黒に全く二分化してはいないが、当然全く同じものなのではなく、イメージ的に表現すれば、(完全に白ではないが)限りなく白いものから、(完全に黒ではないが)限りなく黒いものまで、その間に灰色を挟みながら、途切れることなく連続的に変化している。
そして、これは、哲学と科学と宗教の違いと類似性に限らず、この世界の万物・森羅万象に当てはまる根本的な原理ではないかと考える。東洋思想でいえば、道教の陰陽の思想などにも見ることができるものだ。
25.現代の科学の構造的な問題
現代社会は、中世・近代に比較して、科学技術が非常に大きなウェートをしめる。各国の経済力・軍事力その他の力は、科学技術の開発に大きく依存する。その結果、以前よりはるかに多くの人々が、そして、巨額の資金が、そのために使われる。
そうすると、科学者の活動が、昔のように純粋に、真実の発見への関心によるものばかりではありえなくなった。昔は皆、科学者はアマチュアであって、職業科学者はいなかった。自己の科学的な探究と、自分の経済的な利益や社会的な名誉は必ずしも直結してはいなかった。
しかし、今や、科学者のほとんどは、それを職業とし、企業や公的な研究機関の中で、研究成果をあげて名誉を得る、ないしは経済的な利益を得る、という圧力の中で活動している。それは、他の職業と全く違いはない。
そして、私見では、初期の純粋さを失った、大きくなった後の宗教団体にも同じ現象が起こる。
26.STAP細胞問題の背景
その結果として、本当に真実発見のみを目的にして科学しているのではなく、自分の社会的な存在意義や生活の手段として活動している面も多くなっていく。場合によっては、それほど科学が好きではないのに、職業としては他の分野よりも自分に向いているだろうといったくらいの動機で入る人も少なくないだろう(いや過半数がこうかもしれない)。
そうした中で、論文を多く出せば、その成果が十分に確認される前でも、学会では尊敬されるから、論文の捏造などの科学者の不正が生じる。予算の獲得のためには、自分の研究分野・研究所の将来の可能性を強調する必要があるから、事実上、誇大宣伝・嘘をつく場合もある。そこまでいかなくても、相当に先走ってしまうこともある。昨今の理研のSTAP騒動も、そうした科学の世界の人間的な現象から生じていると思う。
こうして、「宗教と科学」という、一見して対極的な両者の間にも、同じ人間世界の活動として、多くのつながり・類似性があると思う。
27.言葉の問題と無知の知の大切さ
最後に、これまで述べてきたことから、人類の叡智としての哲学・科学・宗教を考えるとしても、言葉とその意味について、よく考えなければならないことがわかる。
第一に、その日本語は、近年の訳語にすぎない。第二に、原語の外国語も今と昔では大きくその意味が変わっている。そして、第三に、今の意味も昔の意味も、そのだいたいのイメージはあるが、明確な定義できない、ということである。
そして、明確に定義できないということは、言い変えるならば、それとそうでないものの区別(例えば哲学と哲学でないものの区別)が明確ではないのである。
さらに言い換えれば、私たちは、言葉があって、それを何となく日常的に用いていても、その言葉の本当の意味となると、それをほとんど理解していないということが非常に多い。そして、本当はほとんど理解していないのに、あたかも理解しているかのように錯覚しながら、それを使っているのである。
だからこそ、哲学にしても、科学にしても、宗教にしても、何が何だかわからない面があると理解しておくことは、なんとなくわかったつもりになって、(極端に宗教ないし科学を)信頼したり、(極端に宗教ないし科学を)否定したりするよりも、より深い智恵を得る土台となると思う。
これは、よく言う「無知の知」ということである。この心境に立つことが、逆に、哲学・科学・宗教といったものを以前より正確に理解する扉を開くことになる。
【※この教本の目次・購入は、こちらから】